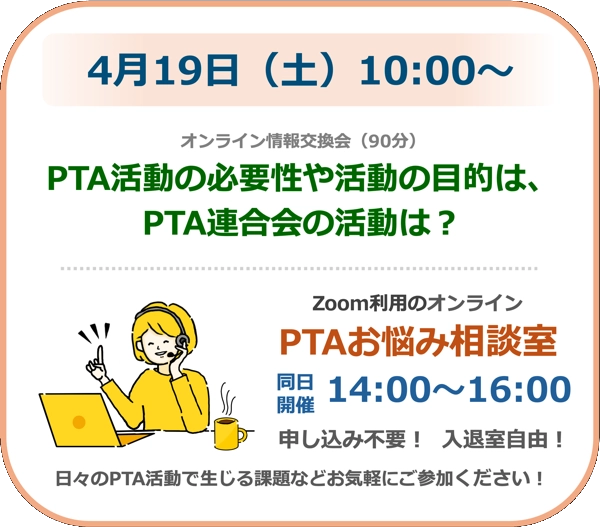性犯罪・性暴力未然防止
できることから取り組もう!

性暴力をする人は、見るからに怪しくて、事前に予想がつくのでは?と思う方もいるかもしれませんが、多くの場合そうではありません。加者害も怪しまれたくないので勤務態度はよく、園や子どもからの評価が高い場合もあります。
さらに、人目につかないような場所や時間帯を選んで、行為に及びます。
お住まいの地域や学校における性暴力未然防止に取組状況について今一度確認してみましょう。また、保護者として、できることから取り組むことで、性暴力が発生しづらい、子どもにとって 安全な環境づくりを粘り強く支援していきましょう。
文部科学省の通知では
近年、国では教員による児童生徒に対する性犯罪・性暴力等に係る対策を進めており、2021年には教員による児童生徒性暴力防止法が制定され、翌年4月に同法が施行されています。文部科学省では2022年3月に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を策定、採用権者が採用候補者の免許失効歴を確認できるツールを整備したり、啓発動画を作成したりと、対応を進めています。
また、学校の教員に限らず、保育士や塾講師など、子どもと接する職業に就く者による子どもへの性暴力を防ぐために、雇用する側が対象者の性犯罪歴を確認できるようにする「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」が2024年6月に成立し、こども家庭庁を中心に導入に向けた議論がなされています。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について、さまざまな対策が既に実施されていますが、2023年度に性犯罪や性暴力、セクハラ行為で懲戒処分などを受けた公立の小中学校や高校などの教育職員はあわせて320人となり、今の形で統計を取り始めた2011年度以来、過去最多となっています。
こうした中、20257年7月1日付、文部科学省の通知「各教育委員会において取り組んでいただきたいこと」には、以下のような記載(抜粋・要約)があります。
研修実施、防止対策と相談体制、厳正処分
研修の実施等
- 各教育委員会におかれては、児童生徒性暴力等の防止等に関して、教師の服務規律の確保を徹底するとともに、 今一度、教員性暴力等防止法及び基本指針を確認し、教師による児童生徒性暴力等の防止のため研修を改めて実施するなど、必要な措置を講ずること
- 研修等に当たっては、以下の点を含め、今一度周知を徹底すること
- 教員性暴力等防止法第2条第3項各号に規定する行為は児童生徒性暴力等に当たり原則懲戒免職処分の対象となること
- 児童生徒性暴力等については、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無は問わないこと
被害の未然の防止対策等
- 被害を未然に防止する観点からは、教師と児童生徒等が第三者の目が行き届きにくい環境となる場面をできる限り減らしていくことが重要
- 執務環境の見直し等による密室状態の回避や組織的な教育指導体制の構築などの措置を講じること。 盗撮防止にあたっては、教室やトイレ、更衣室等の定期的な点検を行うことや、教室等を常に整理整頓し、カメラ等を設置できないような環境にしていくことが重要
- 教師がSNS等を用いて児童生徒等と私的なやりとりを行ってはならないことはもとより、以下の点を徹底すること。
- 教師個人のスマートフォン等の私的な端末で児童生徒等を撮影することのないようにすること
- 学校所有等の端末で撮影する場合であっても児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出すことのないようにすること
相談体制の整備等
- 児童生徒等や教師等に対する定期的なアンケート調査を実施すること
- 被害児童生徒やその保護者等が安心して相談できる環境の整備に取り組むこと
- 各教育委員会等が設置する相談窓口等を改めて児童生徒や保護者に対してしっかりと周知を行うこと
- 相談があった場合には各教育委員会において、警察等の関係機関と迅速に連携することも含めて、適切に対応すること
厳正な処分
教師による児童生徒性暴力等が行われる事態が生じた場合には、教員性暴力等防止法及び基本指針に基づき、原則として懲戒免職にするなどの厳正な処分を徹底すること関連情報
全都道府県・市区町村教育委員会を対象としたアンケート調査 ≫
子どものサインを見逃さない
性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、特にこどもの頃に被害に遭うなど被害時の年齢が低いほど、その心身を長期間にわたって深く傷つけるものとなります。
その一方で、こどもは性暴力の被害に遭っても、それを性被害だと認識できない場合があることや、加害者との関係性などから誰にも相談できず、被害が潜在化・深刻化しやすいことが指摘されています。
一刻も早く被害の継続を防ぎ、こどもたちを性被害から守るためには、周囲の大人がこどもたちの発するサインを見逃さないようにすることが大切です。 性暴力の被害の影響の現れかたはケース・バイ・ケースであるため一概には言えませんが、性被害に遭ったこどもには次のような心身の不調や問題行動が見られるといわれています。
性暴力被害に遭ったこどもが見せるサインの例
からだの変化
- 頻尿、おねしょ
- 集中力の欠如、学力不振
- 体調不良(頭痛、腹痛、吐き気、倦怠感など)
- 不眠(夜更かし、悪夢を見る、一人で眠れないなど)
- 性器の痛みやかゆみ
- 食欲不振、過食
こころの変化
- ふさぎこむ、元気がない、無気力
- 過剰に甘えようとする
- 集中力の欠如
行動面の変化
- 自傷行為、リストカット
- 多動や暴力的行為
- 非行(飲酒、喫煙、家出など)
- 人との距離が近い、不特定多数の人と安全でない性行動を繰り返す。
もし、こどもにこのようなサインが見られたら、その心身の不調や問題行動などの背景にあるトラウマ(心的外傷、心の傷のこと)を理解して、適切に対応することが重要です。
なお、性暴力の被害に遭っても、全くサインなどは現れず、ふだんどおり元気にしているこどももいます。こどもが発した言葉の中にも、何か気になることがあれば、留意しておくことも必要です。
関連情報
子どもの性被害に気付いたら ≫
性被害を知ったら、どこに相談すべき ≫
こんなときには支援センターに相談 ≫
子どもたちに伝えておくべき事
子どもを性犯罪・性暴力等の被害から未然に守ることも私たち身近な大人の役割です。いざというときに子どもが性犯罪・性暴力等から自分の身を守れるように、また、性犯罪・性暴力等の加害者となることがないように、幼児期から折を見て次のことを伝えるようにしてください。
子どもたちに伝えておきたいこと
- 水着で隠れる部分(プライベートゾーン)は見せない・触らせないこと。
- 相手のプライベートゾーンを見ない、触らないこと。
- イヤな触られかたをされそうなときは、「イヤだ」、「やめて」と言ってもいいこと。
- イヤなことをされたら、すぐに大人に相談すること。
- 自分は大切に扱われる存在で、相手も自分のように大切に扱われるべき存在であること。
性犯罪・性暴力等の被害に遭った子どもは、そのことを親や家族、身近な大人に知られることを恐れ、誰にも相談できずに、被害に遭い続けてしまう場合もあります。
身近な人に知られることなく、専門家に相談できる窓口があることを、日頃から伝えておくことも大切です。
一番大事なこととして、小さな頃から、自分のからだとこころは、自分自身のものであるということを、繰り返し、しっかりと伝えましょう。
そして、子どもが性的な行為についても理解できるような年齢になってきたら、同意のない性的な行為は性暴力であるということについても話し合うようにしましょう。
子どもの異変やSOSにいち早く気付けるような関係・環境をつくるために、日頃から家庭内でコミュニケーションを取り、子どもの言葉にしっかり耳を傾けることが大切です。
また、子どもにとって「身近な大人」は、保護者や家族だけではありません。
日常的に接する機会のある子どもの行動や態度に不自然な点や異変はないか、性暴力の被害を受けているサインはないか、子どもと関わりのある全ての大人が注意深く見守りましょう。
不正のトライアングル
不正のトライアングルとは
不正のトライアングルとは、アメリカの犯罪学者ドナルド・R・クレッシーが提唱した理論で、不正行為が発生する要因を「機会」「動機」「正当化」の3つに分類したものです。
不正のトライアングル理論は、性犯罪・性暴力等を含む不正行為のメカニズムを理解する上で有効なツールです。この理論を参考に、社会全体で不正を未然に防ぐための対策を講じることが重要です。
- 機会(Opportunity)
不正の実行を可能にする客観的な環境がある状態で、監視体制の不備や、不正が発覚しにくい状況などが該当します。 - 動機(Motive)
不正行為を行うに至る内的な誘因で、例えば、経済的な困窮、ストレス、不満などが挙げられます。 - 正当化(Rationalization)
不正行為を自分の中で正当化する思考過程で、「自分だけならバレない」「誰にも迷惑をかけない」といった考え方です。
また、行き過ぎた勝利至上主義が現場の指導者に結果を求める重圧となり、倫理観の欠如を引き起こす一因ともいわれます。
性犯罪・性暴力等における不正のトライアングル
性犯罪・性暴力等における不正のトライアングルでは、
1. 機会
- 被害者が抵抗できない状況(人気のない場所や一人暮らしの家など)
- 監視カメラや防犯設備がない場所
- 加害者が被害者の弱みを知っている
- 加害者が支配的な立場にある
2. 動機
- 性欲、支配欲、性的コンプレックス
- ストレスや不満の発散
- アルコールや薬物による影響
3. 正当化
- 被害者は誘惑した
- 被害者は抵抗しなかった
- 自分は悪くない
- 誰にも知られない
- 同種の違法行為を行う仲間の存在
教育職員の性犯罪・性暴力等の抑止に向けた
不正のトライアングル理論の活用
不正のトライアングル理論は、性犯罪・性暴力の防止にも活用できます。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
機会の排除
- 物理的な死角の排除
- 管理者等による不規則なタイミングでの巡回
- 空き教室については施錠と鍵の管理を徹底
- 防犯カメラの設置(トイレや更衣室の前)
- カメラ設置後の適切な運用(定期的な確認体制、記録の管理)
- 内部規則の徹底(管理者がルールを軽視する場合の自治体等の相談窓口)
- 定期的な配置換え
- 複数体制での保育の徹底
動機の抑制
- ストレス軽減のための相談窓口
- アルコールや薬物依存への対策
正当化の防止 … 教育職員を対象
- コンプライアンス教育を実施
- 性犯罪・性暴力等に関する正しい知識の普及
- 被害者の心情への理解を深める教育
- 内部通報制度の整備(匿名対応)
正当化の防止 … 児童生徒を対象
- 性暴力に関する知識の教育
- 相談窓口や相談方法を保護者や児童に周知
- 1人1台端末活用などでの定期的なアンケート実施
ある人が、既に性犯罪・性暴力等を正当化している場合、正当化を否定する情報に接することで直ちに正当化が修正されるとは考えにくいですが、児童生徒に対して性暴力から身を守ることを教える立場に立てば、性犯罪・性暴力等を正当化する態度を維持することが難しいことを自覚する機会が考えられます。
教員を対象とした研修に加え、児童生徒を対象とした「生命(いのち)の安全教育」を定期的に実施することは、正当化の防止に寄与する大切な取り組みです。
まず、できることから取り組もう!
不正のトライアングルの考えに基づくと、「機会」「動機」「正当化」がすべて揃うことで、不正が発生します。不正を発生させないためには、不正のトライアングルにおける3要素がすべて揃わないよう、各要素を防ぐことが重要です。「機会」「動機」「正当化」の3要素を防ぐには、具体的にどういった取り組みが必要か、自治体だけでなく、保護者としてもできることから考えましょう。
保護者として知っておくべきこと
- 性犯罪・性暴力等の抑止に向けて、国や自治体はどのような取り組みをしているの? ≫
- 性犯罪・性暴力等の被害に遭った子どものサインを見逃さないためには? ≫
- 子どもを性犯罪・性暴力等の被害から未然に守るために、子どもたちに、あらかじめ伝えておとくべきことは? ≫
学校内を点検してみよう!
性犯罪・性暴力等防止に「機会の排除」は重要です。
まず、学校内における施設点検を保護者主導でスタートしてみてはどうでしょうか。
地域によっては、教育関係者、警察関係者、児童福祉関係者、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、学識経験者等多様なメンバーで実施している事例もあります。
学校内における危険箇所の点検とあわせ、性犯罪・性暴力等防止としての物理的死角をチェックを行い、学校や教育委員会に必要な対策を相談しましょう。
チェック結果に対する具体的な対応としては、次のような事例があります。
また、定期的な点検の実施は、犯罪抑止につながるとも考えられます。
- 小窓が展示物等で塞がれており教室外から見えない状態を改善
- 室内を見えなくしているカーテンの取り外し
- 擦りガラスを透明ガラスに変更、大窓の設置
- 外から目が届かない室内奥部を視野に入れるためのミラーを設置
- 使わない部屋の施錠管理徹底
関連情報
② 施設・事業所環境整備 ≫
安全点検:転落や落下の可能性 ≫
取り組み状況を確認しよう!
教育職員等による児童生徒に対する性犯罪・性暴力等の防止等については、文部科学省やこども家庭庁などを中心にさまざまな対策が既に実施されています。一方で、都道府県、市区町村単位の教育委員会での取り組み状況には、少なからずばらつきがあります。
性犯罪・性暴力等の防止等に係る取り組みは、地域の教育委員会だけでなく、学校として必要な取り組みも少なくないありません。保護者としては、子どもたちが通学する学校において、必要とされている取り組みが適切に実際されているかを見守る必要があります。
性犯罪・性暴力等の被害が起きてからの対応も重要ですが、被害撲滅の観点では、不正のトライアングルの3要素「機会」「動機」「正当化」を防止すること大切です。是非、地域や学校における性犯罪・性暴力等の防止に関する取り組み状況を確認しましょう。
子どもに聞いてみる
- 子どもたちのへの定期的なアンケート調査は?
- 学校における「生命(いのち)の安全教育」は?
- 小学生等を対象にプライベートゾーン等の啓発は?
- 子どもの相談窓口の設置や周知の状況は?
- 児童生徒が常日頃からアクセスする頻度の高いブラウザの初期ページやポータルサイトなどへの掲載
- 相談窓口に関する情報のブックマークや、端末のデスクトップなどへの掲載
- 1人1台端末から直接相談できる相談窓口(チャット、心の健康観察など)の整備
学校などで聞いてみる
- 教員等の研修の頻度や内容は?
- 外部講師による研修が行われているかを?
- 教員等への定期的なアンケート調査は?
- 保護者の相談窓口の設置や周知の状況は?
- 被害が疑われる場合の対応は?
- 養護教諭を含む教職員の対応は?
- 教育、保育等の業務に従事させないなど事後の防止対策は?
教育職員の性犯罪・性暴力等