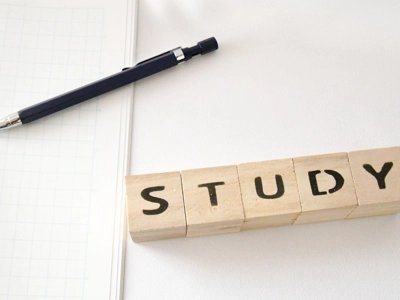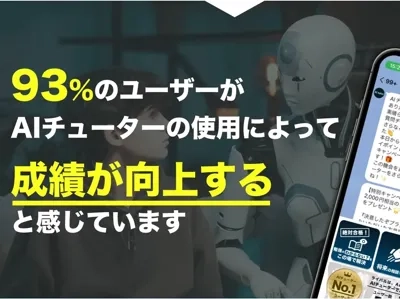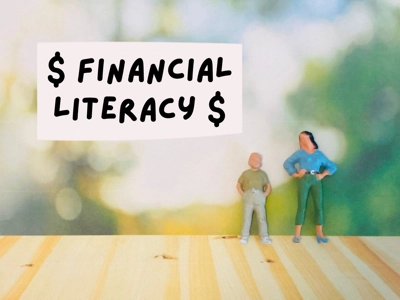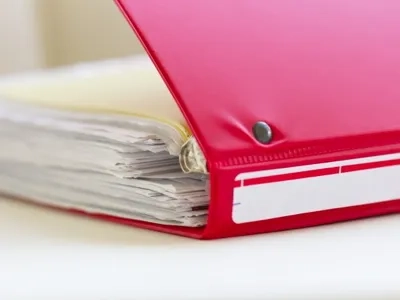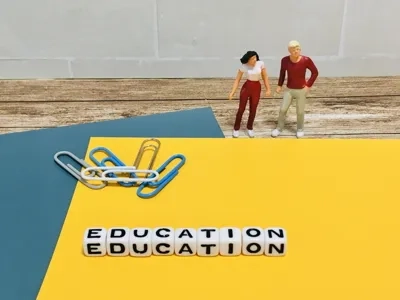教育

トップメニューの他、以下のジャンル別メニューも利用いただけます。
全Pからのお知らせ
セミナーやイベント、相談会
- オンライン開催が主体、お気軽ご参加ください!セミナーやイベント、相談会
情報収集・集約、発信・共有
調査研究やアンケート
- 第1回調査 全P教育施策アンケート中学校部活動の地域展開
- 2025年 保護者アンケート(学校別集計)任意加入説明、PTA会費と会費徴収
全国PTA連絡協議会について
全国PTA連絡協議会について
PTA連合会や単位PTA関連の活動
規約など
- 団体会員規約と個人会員規約会員規約
その他
会員制度やサービスのご案内
会員団体の一覧
-
会員一覧 … 単位PTA会員の会員校とPTA連合会会員一覧 PTA連合会名と単位PTA会員の学校名
-
会員一覧 … PTA連合会会員の会員校会員一覧 PTA連合会別の学校名
-
会員一覧 … 地域団体会員会員一覧 地域団体名
会員登録をご検討中の皆様へ
- 会員登録のご案内単位PTA や PTA連合会の皆様へ
- 会員登録のご案内地域団体 や 個人の皆様へ
法人賛助会員
会員サービスのご案内
PTAメール
調査研究・アンケート
調査研究事業
第1回調査 … 全P教育施策アンケート
-
調査概要、要約や提言文書など中学校部活動の地域展開 調査概要
-
1,004人の皆様から貴重なご意見の層別集計など中学校部活動の地域展開 調査結果 ①
-
国への要望やパブコメ、本調査へのご意見など中学校部活動の地域展開 調査結果 ②
- 第1回調査 関連情報中学校部活動の地域展開
第2回調査
- 第2回調査 関連情報子どもによるSNSの利用に対する認識
-
未成年のSNS利用を考えるSNSは厳格な管理へ、2025年は歴史的な転換点
-
未成年のSNS規制の論点や抗議活動SNS規制導入 直後のオーストラリアでは?
-
未成年のSNS規制を考える日本のSNS規制はどうあるべきか?
-
目的にあわせて複数の対策を併用子どものSNS利用を適切に管理するには
-
子どもに安心してスマホを渡すためのツールお子さまのスマホにはコドマモ
-
小学校高学年のスマホ所有率は4割超にスマホをいつから持たせているの?
-
ルールのポイントや例、保護者の責務スマホ利用のルール
-
保護者の把握、スマホの影響やトラブルスマホ利用におけるリスクやトラブル
-
有害サイトアクセス制限サービスフィルタリングをご存じですか?
-
自分専用のスマホを持つ小学生が増加中SNS利用の低年齢化とリスク認識
-
保護者アンケート(学校別集計)
- 2025年 保護者アンケート 学校別集計結果任意加入説明、PTA会費と会費徴収
日々のニュースから
ICTツールの利活用
ICTツールの導入
-
利用しやすいメジャーなICTツールICTツールを使ってみよう!
-
オンライン、コミュニケーション、グループウエアなどPTAで使いやすいICTツール
-
ICT化したいなぁ ICT化したけどうまくいかないなぁPTAでのICT化を検討する際に
-
非営利団体向け特別プランLINE WOKRSとは
ICTツールの活用
Googleの活用
オンライン会議の利活用
-
導入準備から導入方法、活用法までPTAでもZoomを活用しよう! 2026
-
オンライン会議ツール導入を応援します!PTAでもオンライン会議
-
PTA別平均会議時間、年間会議開催回数PTAでのオンライン会議の利用状況
-
Zoom、Meet、Teams の特徴は?Web会議ツールを比べてみた
-
リアルとオンライン併用のハイブリッド形式でPTA会議のハイブリッド開催
- 初めて利用さる方から主催者までZoom 利用マニュアル
ICT利用の環境整備
- PTA名義で契約可能!Wi-Fiルーターとスマートフォン
- 独立した団体として学校に依存しない会費集金PTA会費集金サービス
情報共有や資料 … PTAの皆様に
PTA活動 スマート化
-
PTA活動の課題と今後の変化これからのPTAのありかた
-
サークル制とサポーター制、コア型、PTCAなどこれからのPTAって、どんな形?
-
契約の切替、PTA活動助成制度、不登校保険などPTA役員として知っておくべき補償制度
-
無料のグループコミュニケーションアプリPTA活動に便利! BANDとは?
-
PTA活動のスマート化Comunii for PTA とは?
-
PTA会長職を引き受けたものの … どうすれば?新任PTA会長 ハンドブック
-
全国各地の情報をまとめてご案内全国各地のPTA運営ガイドのご紹介
- PTAで導入子どもの安心と安全
-
見守りシステム「ミマモルメ」と「OTTADE!」ICタグを利用した子どもの見守り
-
見守りシステム 地域での導入検討にあたって地域で導入 子ども見守りシステム
-
みんなで、みまもる 地域の新しいみまもりのあり方otta … PTAで導入 子どもの見守りシステム
-
導入負担が軽減できるPTA活動助成制度otta … 子どもの見守り PTA専用プラン
-
繰越金の有効活用に!otta … 子どもの見守り
-
いざという時に子どもたちの居場所が分かるOTTA 見守りシステム 導入事例
-
緊急連絡先カードは紙からクラウドへmain … レスQR
-
緊急連絡先カードの進化系main … レスQRご利用ガイド
-
PTA活動のアップデート
-
PTAは任意団体であり、加入も任意です!PTA活動のアップデート
-
現状把握、活動のスマート化 から 任意加入へ強制PTAから任意加入制に移行するには
-
時代背景、改革にあたっての課題PTA改革を進めるには
-
PTA規約も時代にあわせたアップデートが必要です!PTA規約/会則のアップデート
-
市区町村郡PTA連合会からの退会も選択肢連合会加盟継続を考えるための整理
PTA運営課題と向き合うための解説 ①〜⑭
- PTA運営の課題と対応 解説 ①〜⑭
- ① 担い手不足と負担軽減の考え方
- ② 活動量と時間負担の見直し方
- ③ 任意加入の説明と加入意思確認の進め方
- ④ 活動をスリム化する手順と注意点
- ⑤ クレーム対応とコミュニケーション設計
- ⑥ PTAのデジタル化(DX)の進め方
- ⑦ 多様な家庭状況に配慮した運営のポイント
- ⑧ 引き継ぎの標準化と運営の再現性
- ⑨ PTAの目的と存在意義を言語化する
- ⑩ これからのPTAのあり方 任意加入時代の設計
- ⑪ コンプライアンス … 任意団体としての整理
- ⑫ コンプライアンス … 個人情報保護の実務
- ⑬ コンプライアンス … 会費と会計の基本
- ⑭ コンプライアンス … 事故を防ぐルール整備
PTA 会計/会費
-
希望される会員団体の皆様にPTA活動助成制度のご案内
-
会費集金に関する最新動向、サービス比較会費の集金は学校でなく、PTAが独自に集金!
-
会費や会費の蓄積である繰越金の適切利用のヒントPTA会費や繰越金の有効活用に
PTA名義の口座開設、デビットカード
情報共有や資料 … 保護者の皆様に
子ども
子どもの教育
子どもの教育
教育に関する動向
子どもの教育費
教育の内容
教育関連の調査
部活動の地域展開
PTA活動のアップデート
-
PTAは任意団体であり、加入も任意です!PTA活動のアップデート
-
現状把握、活動のスマート化 から 任意加入へ強制PTAから任意加入制に移行するには
-
時代背景、改革にあたっての課題PTA改革を進めるには
-
PTA規約も時代にあわせたアップデートが必要です!PTA規約/会則のアップデート
学校
教育職員の性犯罪・性暴力等
-
立場を悪用しての性犯罪・性暴力等の事案が増加性犯罪・性暴力等に係る教育職員の懲戒処分等
-
事例集、啓発・研修用動画、教育職員性暴力等防止法性暴力等防止に向けた国の施策
-
性犯罪歴の確認制度、2026年12月に運用開始予定こども性暴力防止法(日本版DBS)
-
文部科学省による児童生徒性暴力等防止推進事業性暴力等防止に関する取組事例集から
-
周囲の大人ができること子どもを性被害から守るために
-
こども家庭庁 児童対象性暴力防止の横断指針に見る性暴力未然防止に向けたルールや取組
-
服務規律等の整備や周知、施設の環境整備、研修など性暴力未然防止に向けた取組事例
-
子どもにとって安全な環境づくりの粘り強い支援が大切!性暴力未然防止 できることから取り組もう!
-
安心と安全
情報共有や資料 … 地域の皆様に
地域活動
地域と子ども
教育職員の性犯罪・性暴力等
-
立場を悪用しての性犯罪・性暴力等の事案が増加性犯罪・性暴力等に係る教育職員の懲戒処分等
-
事例集、啓発・研修用動画、教育職員性暴力等防止法性暴力等防止に向けた国の施策
-
性犯罪歴の確認制度、2026年12月に運用開始予定こども性暴力防止法(日本版DBS)
-
文部科学省による児童生徒性暴力等防止推進事業性暴力等防止に関する取組事例集から
-
周囲の大人ができること子どもを性被害から守るために
-
こども家庭庁 児童対象性暴力防止の横断指針に見る性暴力未然防止に向けたルールや取組
-
服務規律等の整備や周知、施設の環境整備、研修など性暴力未然防止に向けた取組事例
-
子どもにとって安全な環境づくりの粘り強い支援が大切!性暴力未然防止 できることから取り組もう!
-
安心と安全
サービス
- 連絡や広報に便利なツールコミュニケーションツール
- 活動のスマート化に地域団体会員対象ITライセンス支援制度
- 地域の皆様に使いやすい保険・補償制度
- ご家庭で加入 … PTA未加入でもOK園児・児童・生徒総合補償制度
- 選べる親子のための保険のご案内ご家庭で加入 … 組み合わせ自由な4種の少額短期保険
情報共有や資料 … 子どもの教育に関する情報
教育に関する動向
子どもの教育費
教育の内容
教育関連の調査
部活動の地域展開
情報共有や資料 … 学校や教育課題に関する情報
学校と安全
学校内における安全
通学路等の安全
学校、PTA、地域
地域と学校
制度や教員の課題
働き方改革
学校教員の待遇改善
教育の課題
事例紹介 … 活動のヒントに
改革事例 … 単位PTA
改革事例 … PTA連合会
PTA 活動事例
サービス 利活用事例
よくあるご相談 … FAQ
PTA活動やPTA運営
ICT導入や利活用
サービスや事業
PTAや地域団体の皆様に
各種サービスのご案内
- PTA名義で契約可能!Wi-Fiルーターとスマートフォン
- PTA会計のスマート化会員対象ネットバンクとデビットカード
- 連絡や広報に便利なツールコミュニケーションツール
活動をサポート
- PTA活動をよりスマートにアンケート実施支援やPTAメール活用
お子さま・保護者の皆様に
保険・補償制度
- PTAで加入 … PTA保険や個人情報漏えい補償PTA団体補償制度
- 当協議会に会員登録のある学校園の皆様園児・児童・生徒総合補償制度
- 会員登録のない学校園の皆様やPTA未加入の皆様園児・児童・生徒総合補償制度
- 不登校保険に関するご案内学びの継続支援制度 … 2026年開始
- ご家族で加入 … 組み合わせ自由な保険選べる親子のための保険
保険や補償制度
会員登録のあるPTA団体の皆様へ
関連情報 … 保険・補償制度
-
契約の切替、PTA活動助成制度、不登校保険などPTA役員として知っておくべき補償制度
-
PTA補償制度の切り替えなどPTA補償制度のご利用にあたって
-
保護者の皆様、PTA団体を対象とした団体契約補償制度のご案内
-
希望される会員団体の皆様にPTA活動助成制度のご案内
関連情報 … 保護者の皆様に
PTA団体補償制度 … PTAが加入
お子さまの団体補償制度 … ご家族で加入
- 当協議会に会員登録のある学校園の皆様園児・児童・生徒総合補償制度
- 会員登録のない学校園の皆様やPTA未加入の皆様園児・児童・生徒総合補償制度
選べる親子のための保険 … ご家族で加入
地域活動の保険 … スポーツチームや地域団体など
全国PTA連絡協議会へお問い合わせ先
お問い合わせの際には、下記「FAQ」に記載の情報もご確認ください。
トップメニューの他、上記のジャンル別メニューも利用いただけます。
教育
ページの下部へ移動します。
子どもの教育
ニュースや話題
子どもの教育費
子どものキャリア教育
子どもの金融教育
SDGs(持続可能な開発目標)
eスポーツと教育
部活動の地域展開
全国学力・学習状況調査
国際比較
学校
学校内における安全
通学路等の安全
PTAと学校
地域と学校
教育の課題
働き方改革
学校教員の待遇改善
国際比較
教育職員の性犯罪・性暴力等
子どもの不登校
不登校保険
子どものいじめ
学校給食費