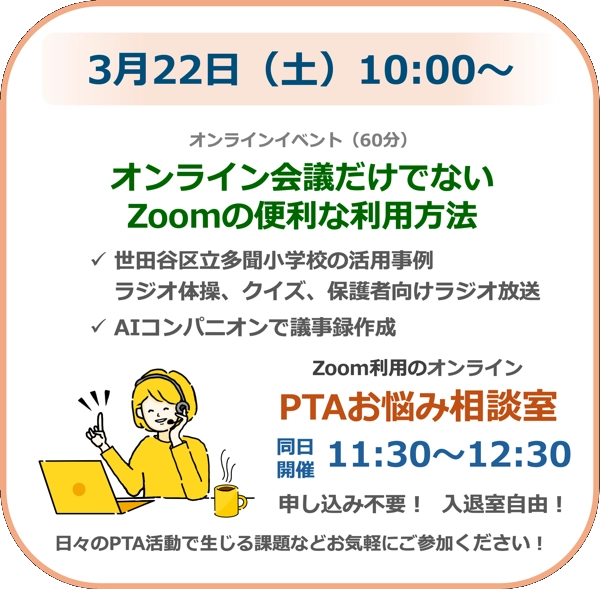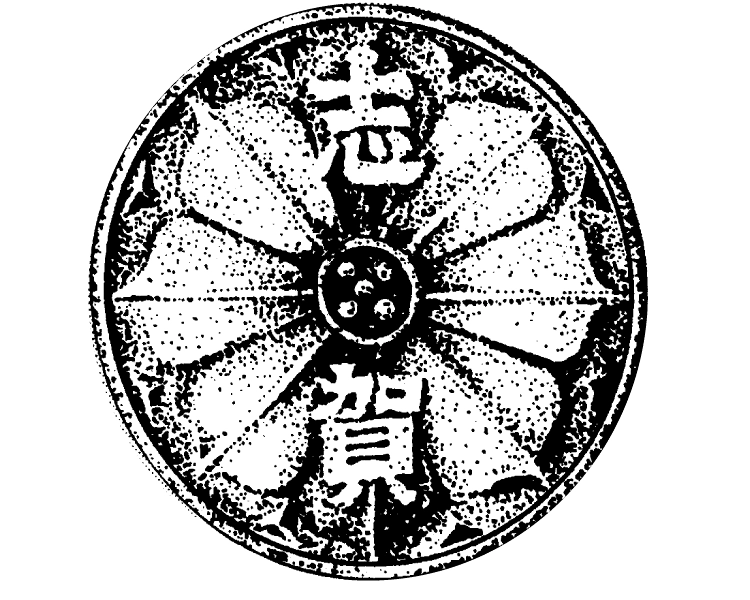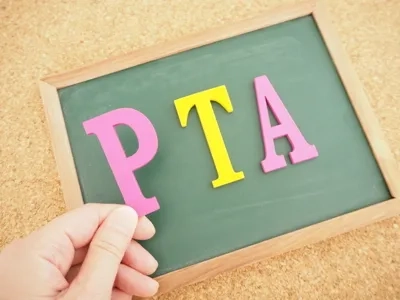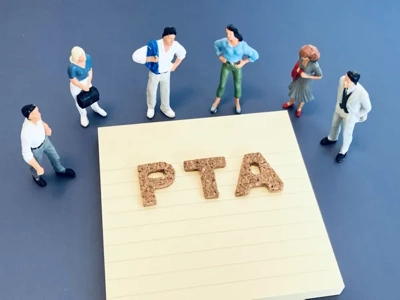これからのPTAって、どんな形?

これからのPTA キーワード
サークル制とサポーター制
今後のPTA活動についてを検討とする際に、最近よく聞く「サークル制」や「サポーター制」とは、保護者の負担軽減と参加意欲向上を目指す、従来の「委員会制」に代わる新しい運営方式です。両者は、保護者が自主的に活動に参加する仕組みという点で共通していますが、活動の形態や組織のあり方に違いがあります。
| サークル制 | サポーター制 | |
|---|---|---|
| 活動の 単位 |
テーマごとの自主的な |
イベントや行事毎の |
| 参加者 | 活動テーマ毎に集まった |
イベント毎に募集 |
| 運営 主体 |
各サークルのメンバーが |
本部が中心での |
ハイブリッド型
サークル制とサポーター制を組み合わせた運営方式や、委員会活動の一部をサポーター制を導入しているPTAもあります。いずれも、ハイブリッド型と呼ばれています。ボランティアセンター
従来のPTA本部を、保護者からのボランティア案やサークル活動の要望を受け付け、サポートする役割の「ボランティアセンター」などに名称変更する事例があります。スポットボランティア制
運動会や見守り活動など、特定の学校行事やイベントのお手伝いを、都度参加者を募集する「スポットボランティア」として実施します。コア型
限られた少人数の「コアメンバー」が中心となって運営する仕組みで、コアメンバー以外の保護者は、イベントの手伝いなど、参加したい活動があるときにだけ関わるなど「やりたい人が、できる範囲でやる」という自主性が尊重された運営です。人的リソースの拡張
学校の保護者と先生だけでなく、人的リソースを広げるPTAもあります。代表的な事例は以下の通りです。- PTCA型組織に移行
- コミュニティスクール(CS)との連携
- P事務と呼ばれるPTA事務員の活用
PTA活動のアップデートに関する皆様からの 情報提供 ≫ をお待ちししています。
これらの新しい運営方法は、保護者の多様な働き方やライフスタイルに対応し、PTA活動の強制感や負担感を減らすための重要な改革と捉えられています。
いずれの方法も導入にあたっては、保護者や教職員との十分な話し合いを重ね、慎重に進める必要があり、PTA規約の見直しなども必要となります。
自分達の地域や学校として必要な改革や取り組みは何かを、当事者意識を持っての検討が必要です。
既に、多くのPTAで、改革に向けた取り組みがなされていますが、解決方法は一つではありません。PTAが解散した後、新たな保護者組織が設立された学校などもあります。組織形態に関わらず、子どもの教育環境の充実や、安全で楽しい学校生活を送れるようPTA活動のアップデートが期待されます。
サークル型のPTA活動
サークル型とは?
サークル型とは、これまでの委員会制度など画一的な組織形態を廃止し、保護者が関心のある活動に任意で参加する仕組みのPTA運営方法で、活動エントリー制などとも呼ばれます。
具体的には、「ベルマーク委員会」「広報委員会」といった固定の委員会を設置せず、特定の活動毎にサークルを設置します。例えば、「花植えサークル」「読み聞かせサークル」などが挙げられます。
本部役員は、会員からの「やりたい・やってほしい」を常時募集するなどして、集まった声を「サークル」として企画します。具体的には、学校側と調整、予算や場所の確保、各サークルの募集窓口業務、活動の取りまとめ、情報発信などを行います。
活動の自由化、任意参加
運動会の手伝い、バザー、校内清掃、保護者研修など、特定の活動ごとに参加者を募集します。保護者は興味のある活動や、都合のつく活動に「できる範囲で、できることだけ」参加する形で、強制的な役割分担やノルマはありません。
「やりたい・やってほしい」が出来てない
深刻なPTA離れ
↓
サークル型のPTA活動で解決!
メリット
保護者の負担軽減
参加が任意になるため、「やらされ感」が解消され、保護者負担が大幅に軽減されます。活動の活性化
実行はそれぞれのサークルで行うので、本当の意味で「やりたい人がやれる時にやれる事をやる」スタイルが実現します。また、参加者が自分の興味や得意分野を生かせるため、活動へのモチベーションが高まります。強制参加の解消
強制加入や、参加が義務付けなどコンプライアンス上の課題解決につながります。デメリット
本部役員の負担
活動ごとに参加者を募ったり、活動内容を調整したりするため、本部役員の負担が増加します。特に、広報、企画、打ち合わせなど、リーダーとなる方の負担と力量にかかる部分が大きいので、世代交代の課題もあります。活動内容の変動
毎回参加者が集まるかどうかは分からないため、活動によっては継続が難しくなったり、内容を縮小したりする必要が出てくる場合があります。特に、見守りや地域連携など、継続した事業運営にはハードルがあります。また、事業計画が立てにくい点もあり、予算編成上の課題も考えられます。コミュニケーションの課題
固定されたメンバーで活動する機会が減るため、保護者間の横のつながりが希薄になるという懸念も指摘されます。ICTツール活用は必須
保護者募集、受付、結果広報など、ICTツールを利用しての運営が前提と考えられます。サポーター制のPTA活動
サポーター制のPTA活動とは、役員や委員会といった固定された役割や強制参加をなくし、イベントや行事ごとに必要なボランティアを都度募集する運営方式のPTAです。参加者は、都合のつくときに、できる範囲で、特定の活動を手伝うことができます。サポーター制PTAの特徴として、
- 在学中に必ず、一人一役といった強制参加がありません。
- 運動会や文化祭、広報誌作りなど、具体的な活動の毎に協力者を募集するため、スポット参加がしやすくなります。
- 「できる人が、できる時に」の仕組みは、定期的な活動が難しい保護者でも参加しやすくなります。
- サポーター募集や集計にITCツール利用した、スマートな運営を行うPTAが多くあります。
- 正副委員長が決まらない委員会のみサポーター制で運営し、決まっている委員会はそのままなどハイブリッド型のPTA運営もあります。
メリット
- 特定の保護者に負担が集中することを避け、多くの人が無理なく関われるようになる。
- 保護者は関心のある活動や得意なこと(写真撮影、調理、後方など)に選んで参加できるため、やりがいを感じやすくなる。
- イベントごとに異なるメンバーと関わるため、委員会制度とは異なり、普段接点のない保護者同士の交流が生まれることがある。
- 従来の役員や委員の負担が減ることで、より前向きで主体的な活動が生まれやすくなる。
- 「役員に誘われるんじゃないか」という心配もなく、サポーターならと気軽に参加できる。
- 委員選出の負担がなくなり、委員履歴・ポイント管理なども不要になる。
デメリット
- イベントの都度、サポーターの募集や調整が必要になるため、本部役員に負担が集中する可能性がある。
- サポーターが集まらない場合、そのイベントや活動は中止せざるを得ない場合があります。
- 参加者が少ない場合は活動規模が小さくなったり、従来のイベントが実施できなくなったりすることもある。
- 活動全体の企画や調整、各サポーターへの指示などを行う本部役員のリーダーシップが重要となる。
- 委員会がなく、引継ぎが出来ないので事業が継続できなくなるリスクがある。
- 「委員から役員」という流れがなくなるので、本部役員の担い手に課題がある。
- 特殊技能が必要になるなど、中心メンバーが常に同じになりがちな活動は、属人化のリスクがある。
- 保護者募集、受付、結果広報など、ICTツールを利用しての運営が前提となる。
コア型のPTA活動
コア型とは?
コア型とは、新しいPTAの運営形態の一つで、PTAを運営するのは、中核グループ(本部総務会や役員会など名称は様々)のメンバーです。中核グループは、保護者会員と教職員会員とで構成され、一般の会員はいません。
グループの運営上、代表者となる会長以外は、予算を管理する会計職のみなど状況に応じて柔軟な組織構造で、グループメンバーがチームとなって運営を行う、既存のPTA組織に囚われない活動が一般的です。
PTAを運営する中核グループの活動は「誰が何をやる」ではなく「全員で動く」が前提となっている場合が多く、特定の役職者が権限を持つ従来の体制に対し、コア型ではメンバー全員がフラットな立場で意見を出し合い運営に反映しやすいなど、風通しの良い組織運営が期待されています。
コア型への流れ
加入率が低下し、また役員のなり手が減少するなど、従来形式でのPTA組織を維持するための活動が困難になっています。また、保護者の負担を軽減が求めらており、非効率な慣習や作業内容の見直しを進め、活動の効率化が必要となっています。参加しやすい環境
主体的にPTA活動に関わりたいメンバーがいても、保護者の働き方が多様化する中、従来のPTA活動の進め方では参加しにくいとの声もあります。共働き世帯が増えるなか、より多くの保護者が参加しやすい仕組みが求められています。事業の運営
メンバー以外のスタッフを必要とする事業をおこなう場合は、サポーター制やサークル制同様、イベント毎にボランティアを募集します。会費に代わる運営費としては、行政等の活動支援補助金、クラウドファンディングなどがあります。
メリット … 保護者
活動負担の軽減
一般の保護者は会員でないため、望まない参加の強制や作業の負担がなくなります。専門性の向上
今後を見守る必要がありますが、活動の中心となるメンバーが固定されることによるノウハウ蓄積、活動の効率や質の向上が期待されます。活動目的の明確化
活動内容の見直しが行われることにより、子どもの学習環境整備や健全な成長支援などPTA本来の目的に沿った、より本質的な活動に集中しやすくなります。メリット … 運営する中核グループ
楽しく活発なPTA活動が実現
コアメンバーだけの運営なので、やる気のあるメンバーによる素早い意思決定は、「それ、おもしろいね!」で、コンプラ課題の減少
加入非加入問題、委員決め役員決め、役割分担や強制など、いくつかのコンプラ課題が解決します。また、会費徴収もないので、学校との委任契約も不要となります。従来型PTAと同じメリット
- 先生や他の保護者と交流する機会があり、学校の様子や運営について深く知ることができます。
- 活動を通じて、学年やクラスを超えた保護者とのつながりができ、情報交換や助け合いの輪が広がります。
- 活動を通して、保護者としてだけでなく、社会人としての学びや成長など自己成長の機会が得られます。
デメリットや懸念点
組織消滅のリスク
少人数による運営のため、全てメンバーが一斉に卒業するなどの場合、組織消滅のリスクが生じます。活動資金
会費を徴収しないため安定した収入を検討する必要があります。また、イベントなどでの都度徴収の場合は、集金事務が発生します。担い手への負担集中
コアメンバーに活動が集中するため、特定の人物に負担が偏る問題が発生する可能性があります。活動への無関心
活動参加の機会が減ることで、多くの保護者の間でPTA活動や学校運営への関心が薄れてしまう恐れがあります。非協力者との分断
義務的な活動は減るものの、活動への関心度合いによって、保護者間の情報格差や分断が生じる可能性もあります。事務処理
毎回、参加者に個人情報保護規程を呈示し、承諾を得て、終了後に破棄する、保険加入手続きなど事業毎に事務処理が必要となります。新しい取り組み
コア型PTAは、一旦切り替えると、従来型への復帰は難しいと考えられます。コア型PTAを導入事例もありますが、まだ新しい取り組みであり、今後の先進事例を見守っていく部分ことも大切だと思います。PTCA型組織への移行
PTCAとは
Parent、Teacher、Community、Associationの頭文字をとったもので、PTAに地域住民が加わった「保護者と教師と地域住民の会」のことです。地域のメンバーとしては、PTAのOB、OGだけでなく、民生委員、老人クラブの代表者、保護司など様々な地域住民が運営や活動に参加します。
PTCAは、地域住民が、学校教育に外側からの支援をするだけではなく、地域の子どもたちは地域で育てるという「共育」の考えを目指す組織です。
PTCAでの運営のメリット
活動の活性化
地域全体で学校をサポートするため、従来のPTAだけでは難しかった活動や、より専門的な活動が可能になります。郷土愛の醸成
子どもと地域とのつながりが深まることで、地域への愛着や関心を育みます。保護者の負担減
強制参加ではないため、保護者は無理のない範囲で活動に参加でき、負担感が軽減されます。保護者同士のつながり
PTA同様、活動を通じて、同じ悩みを持つ保護者同士が交流し、子育ての不安を軽減する効果も期待できます。デメリットや課題
地域資源の偏在
人口が少ない地域などは、協力者や団体の確保が難しい場合があります。参加者
参加者間の参加意欲に温度差がある場合もあり、属人化による継続性のリスク、一部の熱心な保護者や地域の負担が増えるリスクも考えられます。組織運営
PTAの特性上、毎年役員や運営者が変わり、ノウハウや引き継ぎ対策が必要です。また、外部委託や地域の力を活用しすぎると、PTA活動としての自律性が損なわれる可能性があります。PTCA運営のこれから
成功事例の共有
地域特性や人口などにより、PTCA運営のあり方は様々ですが、新しい取り組みがはじまっています。当協議会では、PTA 事例紹介 ≫ で、PTCA運営例をお伝えしています。ICTツールの利活用
これからの組織運営にあたっては、各種連絡、出席調整、会議などICTツールの利活用は必須です。関係者の皆様には、ICTツールの利活用が効率化と負担軽減につながることを理解いただき、ICTツールの導入を前提とした組織運営が必要です。組織の多様化と柔軟な組織運営
学校や地域など立場の違う方々とのコミュニケーションや連携、試行錯誤を許容する文化の醸成など、前例や慣習にとらわれない柔軟な組織運営、あわせて活動の明瞭化が大切です。モチベーション
PTA活動に協力いただく、町会などをはじめとする地域の皆様、地域の中高生や大学生などボランティアに対して、感謝状や何かしらインセンティブを提供するなど、感謝の気持ちをお伝えできる仕組みは、協力者のモチベーションにもつながります。PTCAならではの活動例
PTAのOB・OGだけでなく、地域住民の協力を得ることで、活動の可能性が広がります。環境整備活動
学校や周辺の環境美化に取り組み、花壇の整備などは代表的な例体験学習の提供
地域ならではものづくり体験、お祭り参加、伝統文化体験などの機会を提供世代間交流イベント
地域の大人や高齢者と子どもたちが交流できるイベントを開催、世代間相互理解の機会を提供防犯・防災活動
学校周辺のパトロール、防犯や防災学習会、宿泊体験などを実施キャリア教育
保護者や地域の大人の働く姿に触れるなど、キャリア教育につながる職場見学や職業体験1. 学校・家庭・地域社会が目標を一つにすること
目標を一元化することで、一体となった共育を行うことが可能となります。2. 学校が地域拠点となること
学校が中心になるのではなく、学校が拠点であるという点を大切にします。子どもの教育を学校が中心となって負うということではなく、いわば学校を地域教育センター的なものとして捉えることです。3. PTAを母体として組織化させること
学校と家庭、学校と地域社会を結び教育活動を充実させる取組は以前から行われていました。それを発展させ、学校・家庭・地域社会の三者が、子どもの教育について緊密に連携し、組織的に支援活動を行います。その際はPTAを母体として、無理のない、各地の実情に応じた組織づくりを大切にします。PTCA型運営の関連情報
コミュニティスクール(CS)の活用
コミュニティスクール(CS)とは、学校と保護者や地域住民がともに協力し、連携・協働しながら学校運営を進め、子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校」を実現するための仕組みです。この仕組みは、学校運営協議会を設置した学校を指します。学校運営協議会は、以下のような役割を担います。- 学校運営の基本的な方針の承認
- 学校運営に関する教育委員会または校長への意見申出」
- 教職員の任用に関する教育委員会への意見申出。
メリット
PTAとしての負担軽減と効率化
PTA活動の多くがCSの「地域学校協働活動」に統合されることで、活動内容が整理・精選され、保護者の役割が明確化されます。結果、役員の負担や、仕事・子育てと両立しにくい活動が減り、特定の保護者に負担が集中する状況の改善が期待されます。学校運営への意見反映
PTAが学校運営協議会に委員を出すことで、PTA単独で学校に要望を出すより、学校の運営方針に意見を反映させやすくなると考えられます。地域とのつながりが強化
CSの枠組みでの活動により、PTAは地域住民や団体と協働する機会が増え、多様な経歴を持つ人々とのネットワークが生まれ、活動が活性化します。保護者が卒業しても、地域住民として継続的に学校に関わる仕組みができるため、活動の継続性が高まります。保護者の当事者意識が向上
保護者は、学校運営協議会での議論を通して、学校や地域が抱える課題を共有することで、学校支援活動を「自分事」として捉えるようになり、当事者意識が高まります。デメリットや懸念点
PTAの独自性が薄まる可能性がある
PTAがCSの枠組みで活動する場合、学校運営協議会の決定に沿った活動が中心となり、PTA独自の企画や活動が実施しにくくなる可能性があります。保護者同士の交流や親睦的な機能が希薄化することも考えられます。意見反映の限界
学校運営協議会は、あくまで校長が作成する学校運営の基本方針を承認する役割であり、PTAのすべての意見が反映されるとは限りません。PTAでは、最終決定権のある会長は保護者が一般的ですが、学校運営の最終決定権は校長にあり、PTAとして意見を出しても希望通りにならない場合があります。新たな活動による負担の発生
PTA役員が学校運営協議会の委員を兼任する場合、会議への出席や資料作成など、新たな役割が追加される可能性があります。また、CSの枠組みでの活動により、PTA活動とは異なる時間や労力が求められる場合があります。全保護者の参加意識の格差
学校運営協議会に関わる委員は一部の保護者となるため、適切な広報活動を行わないと、他の保護者に活動が見えにくくなる可能性があります。結果として、「一部の人が決めている」という意識が広がり、活動への無関心層が増えるリスクがあります。PTAの運営をCSの枠組みで行うことで、豊富な経験や地域力などで、PTAが抱える負担や不公平感といった課題を解決し、郷土学習や農業体験など地域性を生かした子どもたちへの学習支援や、登下校の見守り、学校環境の整備や改善がなど、より建設的で地域と連携した活動が可能となります。
一方で、PTA独自の活動の幅が狭まったり、学校運営協議会の運営方法によっては、保護者全体への情報共有や参画意識の醸成が課題となる場合があります。
また、保護者は卒業がありますが、OBや地域の方の発言力が強くなるリスクもあります。
関係者の年齢も幅広く価値観が大きく異なる場合もあり、現役保護者との軋轢などが生じる可能性も考えられます。
コミュニティスクールの活用には、メリットもありますが、懸念点も考えられ、保護者や教職員、地域との十分な話し合いを重ねることが必要です。また、当時者間での合意形成に至るプロセスも大切です。
P事務(PTA事務員)の活用
P事務と呼ばれることもあるPTA事務員とは、保護者の負担軽減を目的としてPTAが雇用する有償の事務員です。主な業務内容は、各PTAによって異なりますが、一般的に次のような事務作業を担います。
- 各種資料(案内文、議事録など)の作成、配布
- PTA会費の入出金管理、予算管理
- PTA役員や会員、学校との連絡調整
- イベントの運営事務
メリット
- 文書作成、会計管理、資料準備などの日常的業務をPTA事務職員が担うことで、役員は企画や運営検討など保護者だからこそできる活動に注力可能
- 長年運営に携わったPTA事務職員の適切なサポートによる、スムーズな組織運営
- 別団体である学校とPTAにおいて、教職員やPTA事務職員の職務分担が明確化
- 法令や会計などに専門性があるPTA事務職員の場合、より適切な運営や会計管理が実現
- PTA事務職員が情報を適切に引き継ぐことで、ノウハウが失われることなく活動の継続性が高まり、効率的な運営が実現
- 役員会の日程調整や学校との連絡など、煩雑な調整業務をPTA事務職員が担うことで、スムーズなコミュニケーションが実現
デメリットや懸念事項
- PTA事務職員を雇用または委託に必要な費用、PTA予算での負担
- 同一人物が、長期に渡って事務を行うことによるPTA活動自体の属人化リスク
- 保護者間の直接的な交流や情報交換の機会が減少するなど、PTAへの関心や活動参加意欲の低下リスク
- 職員を介した情報伝達は、担当者の判断が加わるため、情報伝達の遅延、誤解やニュアンス相違が生じる可能性
- 事務職員の権限や業務範囲曖昧だと、PTA活動内容が不明瞭となったり、不正につながるリスクが生じる可能性
PTA活動のアップデート