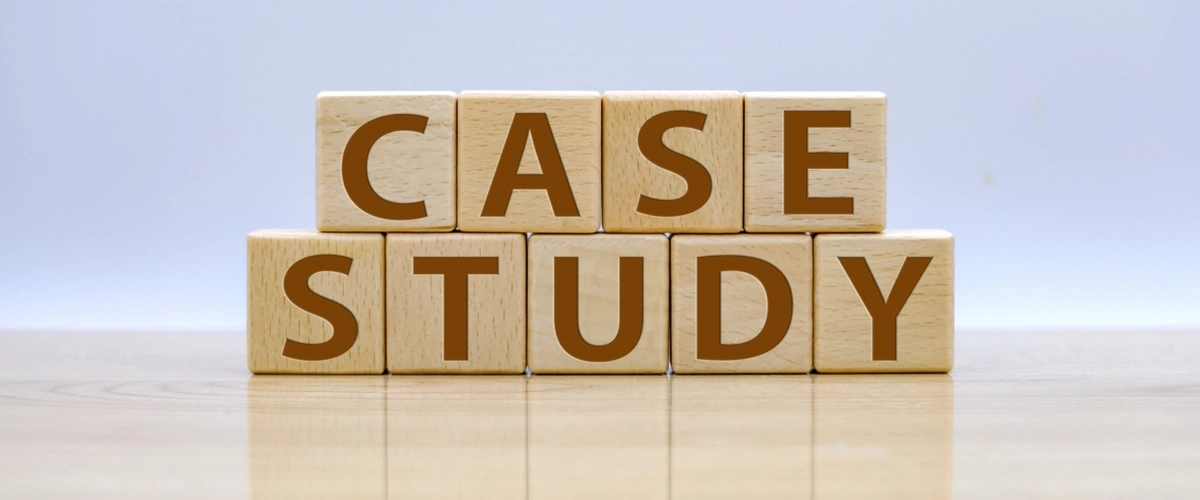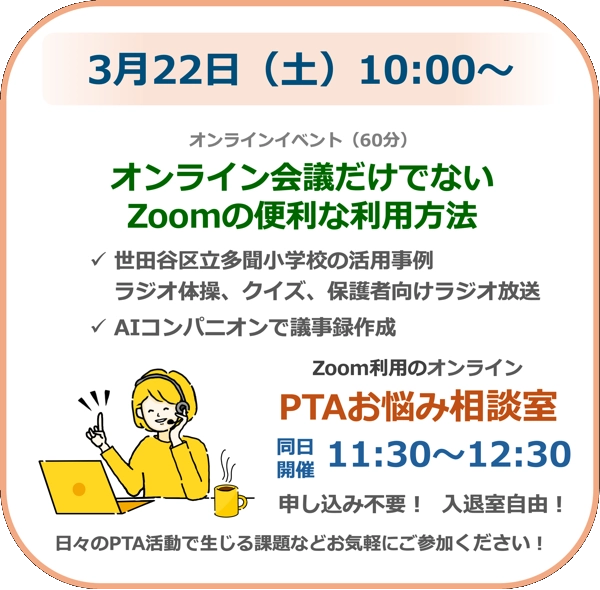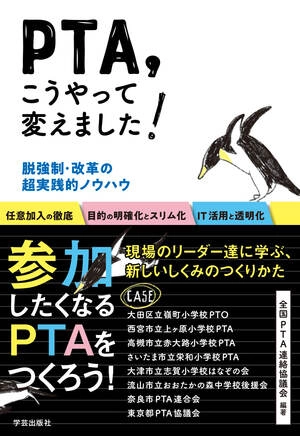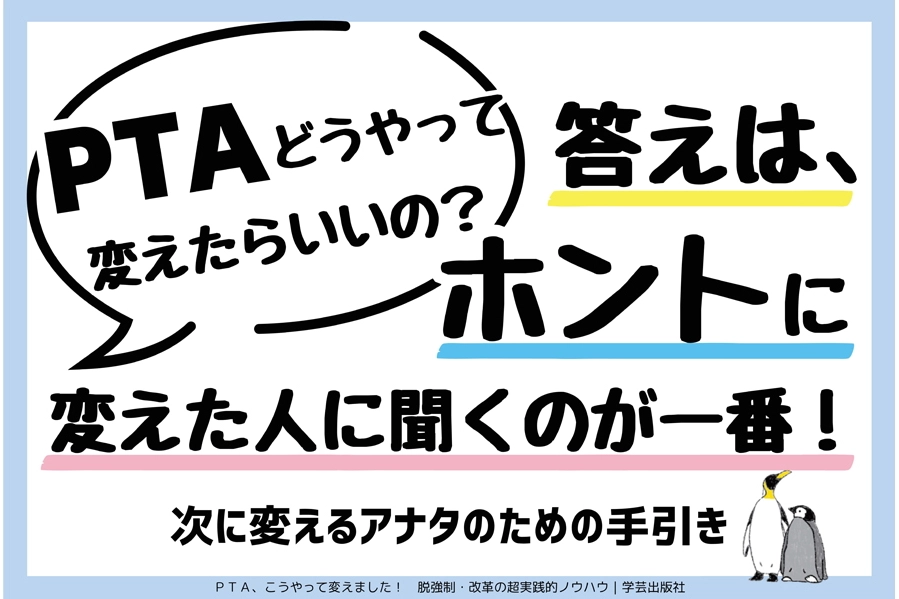松山市小中学校PTA連合会の決断
県Pからの独立で見えた「自立型PTA」の可能性
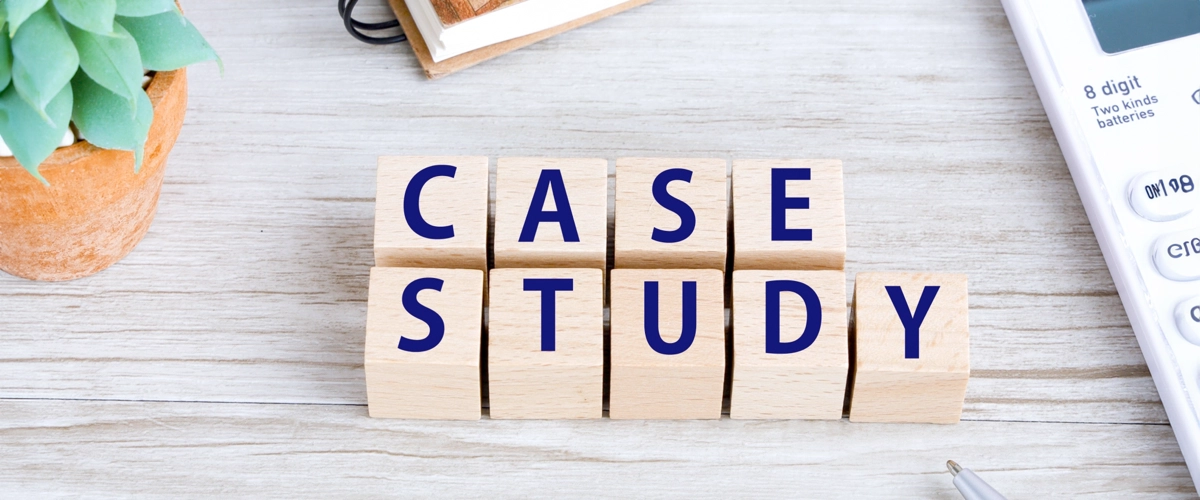
松山市小中学校PTA連合会
自立した運営を目指して
財源を最大限に活かすための決断
松山市Pは、長年加盟していた愛媛県PTA連合会(県P)から、2022年に脱退しました。きっかけは、「松山市の子どもたち、そしてPTAのために、財源を増やして自立した活動をしたい」という思いからです。
当初は県Pに残ったまま独自保険を運営する予定で、理事会でも一度了承を得ていましたが、市Pとしての収入を増やすためにも、「補償制度を独自でやらせてもらえないか」と前年の6月ごろに県Pに打診。
県と市が二つあると加入率が下がるので、県の保険は配らないと約束していましたが、その後、県P側が方針を変更。結果として、独自保険と県Pの保険が二重に存在する状態となり、保険収入の配分も不十分であることが明らかになりました。
県P全体で約1,300万円の保険会社からの収入がある中、市Pに戻るのはわずか約120万円。差額は県全体の事業や人件費に充てられていました。こうした状況を受け、2022年2月、市P理事会は県Pからの脱退を正式決定。「市Pの活動のために使える財源を確保するための選択」だったといいます。
独立で得られた自由度
予算や人員を、市内の活動に集中的に投資
県Pを脱退したことで、市Pの活動に大きな支障はありませんでした。むしろ、県P主催の大会や会議への動員依頼がなくなり、役員や会員の負担が大幅に軽減。その結果、「キッズジョブまつやま」など、独自の事業に予算と人員を集中投資できるようになり、活動の効率化と充実が進みました。
市Pの会費は、独立後、より透明性を高めた形で運用されています。県Pへの加盟費用が不要になったことで、これまで外部に流れていた分を市内の活動に直接還元できるようになりました。さらに、補償制度から得られる制度運営費や事務手数料などの収入を明瞭にし、単位PTAに還元していく仕組みを整備。この助成制度は、市P運営の大きな柱の一つとなっています。
具体的には、
- 「キッズジョブまつやま」やネットモラル授業などの事業費
- 各単位PTAへの活動補助金
- 安全対策や情報発信にかかる費用
市Pでは、「集めた財源をできる限り子どもたちの学びと育ちに直結させる」ことを最優先とし、財源を今後も増やし育てていくものと位置づけています。
松山市Pの強みと活動の厚み
OB・行政・地域とつながる強固な基盤
市Pが安定した活動を続けられる背景には、現役役員だけではなく、OB、行政、地域とのつながりがあります。OBの活躍
子どもたちの参加が1,500人規模で開催される「キッズジョブまつやま」などの大型イベントには、現役役員に加えて多数のOBがスタッフとして参加。スタッフは約150人、グループLINEには250人が登録しており、経験とノウハウが蓄積されています。行政との連携
教育委員会からの委託事業としてネットモラル授業や職業体験事業を実施。委託費が事業運営の安定化にもつながっています。子ども主体の運営
「キッズジョブまつやま」では、保護者同伴なしで子どもが体験に参加。赤いジャンパーを着たスタッフが安全管理を徹底し、子どもの自主性を育む場になっています。地域ブロック制
83の単位PTAを11ブロックに分け、地域ごとの集まりや研修を実施。顔の見える関係づくりを促進しています。 |
 |
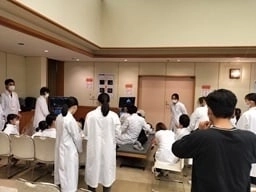 |
 |
 |
財源を活かして未来を築く
持続可能な運営モデルの確立へ
県Pからの独立は、単なる組織変更ではありませんでした。「財源を増やし、それを子どもたちのために最大限活かす」という目的に基づく大きな決断です。独立によって生まれた時間的・財政的余裕は、松山市ならではの独自事業の充実につながっています。今後は、現役とOB、地域と行政が一体となって活動体制をさらに強化し、持続可能な自立型PTAの運営モデルを構築していきます。
松山市ホームページ ≫今後のさらなる取り組みにも期待が高まります。
PTAの皆様へのインタービューなどをもとに、参加したくなるPTAをつくる改革、脱強制・改革の実践的な情報として、1冊の本にまとめています。
これから改革をしていこうという皆様に、少しでも参考になれば幸いです。