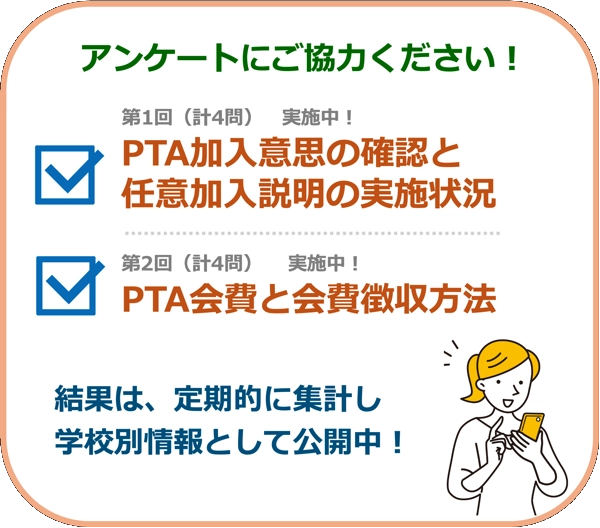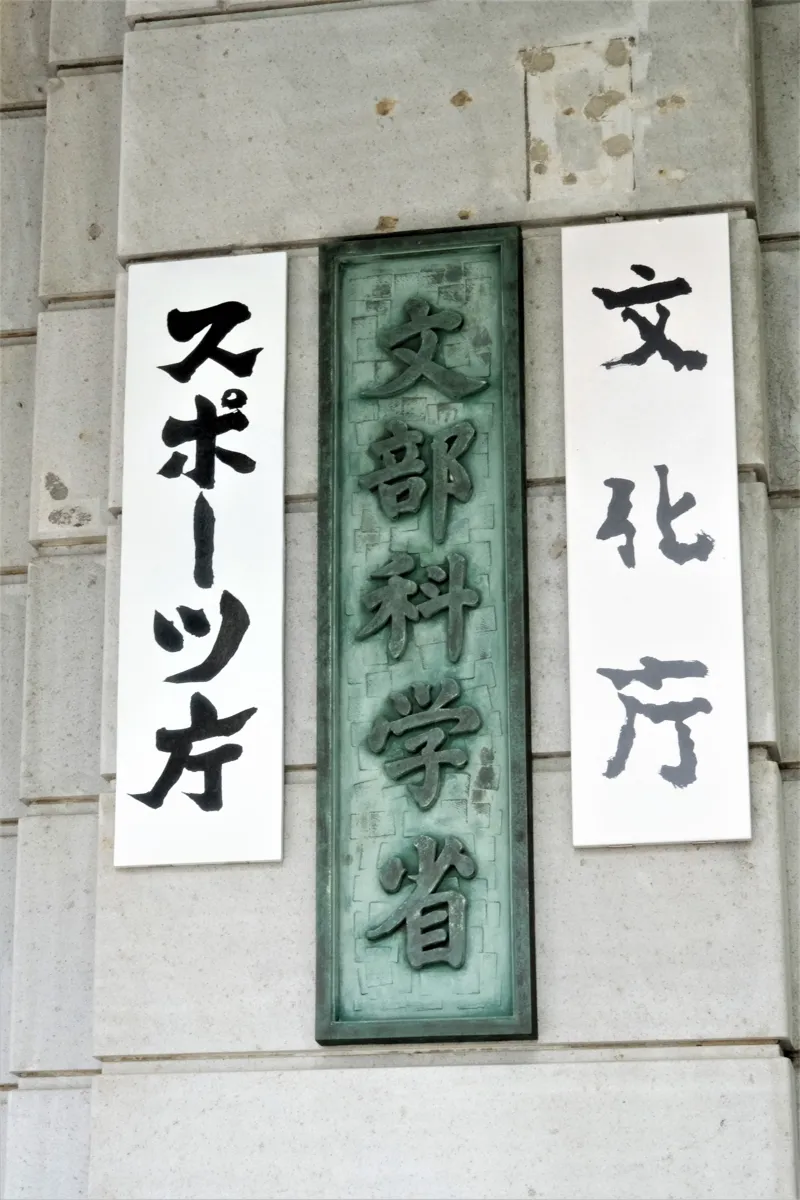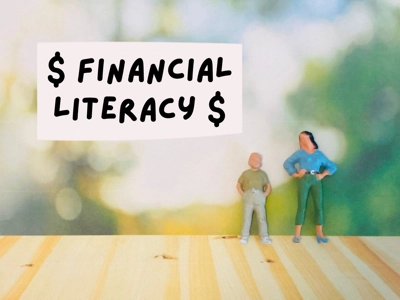近年、キャリア教育の重要性が注目されています!
キャリア教育 小学校では?

キャリア教育とは
キャリアとは?
キャリアとは個人の経歴のことです。
キャリアは仕事やビジネスにおける経歴だけでなく、人の生涯の意味も含まれます。
一般的に、キャリアは仕事の経歴や就職、出世などを指して使われる言葉ですが、「キャリアを積む」のように使われる場合には、生涯やプライベートの意味も含まれます。
キャリアの定義
キャリアとは人の生き方そのものを指しています。人は、他者や社会とのかかわりの中で、職業人、家庭人、地域社会の一員等、様々な役割を担いながら生きている。
これらの役割は、生涯という時間的な流れの中で変化しつつ積み重なり、つながっていくものである。
また、このような役割の中には、所属する集団や組織から与えられ たものや日常生活の中で特に意識せず習慣的に行っているものもあるが、人はこれらを含めた様々な役割の関係や価値を自ら判断し、取捨選択や創造を重ねながら取り組んでいる。
人は、このような自分の役割を果たして活動すること、つまり「働くこと」を通して、人や社会にかかわることになり、そのかかわり方の違いが「自分らしい生き方」となっていくものである。
このように、人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが、「キャリア」の意味するところである。
自分らしく生きることができるようになるための教育
必要となった背景と課題
情報化・グローバル化・少子高齢化・消費社会等
学校から社会への移行をめぐる課題
1.社会環境の変化
- 新規学卒者に対する求人状況の変化
- 求職希望者と求人希望との不適合の拡大
- 雇用システムの変化
2.若者自身の資質等をめぐる課題
- 勤労観、職業観の未熟さと確立の遅れ
- 社会人、職業人としての基礎的資質
- 能力の発達の遅れ
- 社会の一員としての経験不足と社会人としての意識の未発達傾向
子どもたちの生活・意識の変容
1.子どもたちの成長・発達上の課題
- 身体的な早熟傾向に比して、精神的・社会的自立が遅れる傾向
- 生活体験・社会体験等の機会の喪失
2。高学歴社会における進路の未決定傾向
- 職業について考えることや、職業の選択、決定を先送りにする傾向の高まり
- 自立的な進路選択や将来計画が希薄なまま、進学、就職する者の増加
「生きる力」の育成
〜確かな学力・豊かな人間性・健康・体力〜
社会人として自立した人を育てる観点から- 学校の学習と社会とを関連付けた教育
- 生涯にわたって学び続ける意欲の向上
- 社会人としての基礎的資質・能力の育成
- 自然体験、社会体験等の充実
- 発達に応じた指導の継続性
- 家庭・地域と連携した教育
キャリア教育の推進
キャリア・パスポートとは
キャリア・パスポートを作ることで
キャリア・パスポートを作ることによって、子どもは1年を振り返りつつ、改めて考えることができます- 今、何を目標にしているか
- 何が一番好きか
- 今年1年間でがんばったこと
- これからやってみたいこと
- やりたいことを実現するためになにをすればいいか
キャリア・パスポートの引き継ぎ
キャリア・パスポートの書き方や使い方は、各学校に任せられているので、オリジナル教材に近い形になっています。文部科学省では、キャリア・パスポートの引き継ぎについて、
- 学年間の引き継ぎは、原則、教師間で行うこと
- 校種間の引き継ぎは、原則、児童生徒を通じて行うこと
- 小・中学校においては、進学先への確実な引き継ぎに留意すること
- 特に中学校から高等学校への引き継ぎなど、学校設置者が異なる学校への引き継ぎの場合は、特に配慮を要すること
キャリア・カウンセリングとは?
キャリア・カウンセリングとは、子どもたちが自分の意思と責任で進路を選択できるようにするために行う、指導援助のことです。
しかし、多くの学校の先生には「卒業直後の進路決定のための相談」いわゆる「面談」と受け止められてしまうなど、キャリア・カウンセリングが、十分に認識されていないという実態があるようです。
キャリア・カウンセリング計画率は、小学校:5.7%、中学校:55.9%、高等学校:61.6%
学校におけるキャリア・カウンセリング
学校におけるキャリア・カウンセリングは、発達過程にある一人一人の子どもたちが、個人差や特徴を生かして、学校生活における様々な体験を前向きに受け止め、日々の生活で遭遇する課題や問題を積極的・建設的に解決していくことを通して、問題対処の力や態度を発達させ、自立的に生きていけるように支援することを目指しています。
これはキャリア教育の目標と同じです。ただ、キャリア・カウンセリングは「対話」、つまり教師と児童・生徒との直接の言語的なコミュニケーションを手段とすることが特徴です。
小学校における広義の実践
小学校がこれから続く学校生活の基盤として、学校や教師への信頼、そして学ぶことへの喜びを体験する大切な時期であるという認識に立って、教師がそれぞれの子どもの存在を尊重して温かい人間関係を築くことを意味します。
子どもたちとの温かで教育的な人間関係を築くためには、教師は一人一人の子どもとのコミュニケーションを図る能力を向上させることが不可欠となります。
小学校における狭義の実践
子どもたちが新たな環境に移行したり未経験の学習課題に取り組む際には不安も大きく問題を引き起こしやすいことを意識し、単に不安の解消や問題解決だけでなく、新たな環境や課題に勇気を持って取り組めることを目的とした個別の支援のことです。キャリア発達支援そのものと言えるでしょう。
例えば、小学1年生は初めての学校生活に不慣れなために課題や問題を経験する時期ですし、どの学年でも学年始め・学期始めや学年末・学期末には新学級や新学年への適応で問題を経験する時期です。
特に6年生は中学校進学という大きなステップを乗り越える準備のときでもあるので、中学校へ勇気を持って進めることを目指した個別支援は不可欠です。
小学校におけるキャリア教育
自分に気付き、未来を築く キャリア教育
進路の選択・探索にかかる基盤を形成する。
キャリア教育が目指すもの
- 一人一人のキャリア発達を支援します
- 学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させ、学ぶ意欲を向上させます
- 将来の社会的自立・職業的自立の基盤となる資質・能力・態度を育てます
- 望ましい勤労観・職業観を育てます
小学校におけるキャリア教育の目標
- 自己及び他者への積極的関心の形成・発展
- 身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上
- 夢や希望、憧れる自己イメージの獲得
- 勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成
社会的自立の基盤となる諸能力の育成
低学年
日常生活、道徳の時間、特別活動、各教科自分の好きなこと、得意なこと、できることを増やし、様々な活動への興味・関心を高めながら意欲と自信を持って活動できるようにする。
中学年
日常生活、道徳の時間、特別活動、各教科、総合的な学習の時間、外国語活動友達のよさを認め、協力して活動する中で、自分の持ち味や役割を自覚することができるようにする。
高学年
日常生活、道徳の時間、特別活動、各教科、総合的な学習の時間、外国語活動苦手なことや初めて経験することに失敗を恐れず取り組み、そのことが集団の中で役立つ喜びや自分への自信につながるようにする。
なぜ小学校でキャリア教育が必要?
中学校以降のキャリア教育
小学校でのキャリア教育は個々の生徒が「生きる力」を身につけるための学びを中心としていますが、中学校以降になると職場体験学習などの具体的な職業に関する教育へと移行していきます。
高校になると、さらに発展した職業体験をすることでより将来に向けた本格的な学びを深めるようになります。
ただし、中学校や高校のキャリア教育は具体的な職業選択を目指すものではなく、学校での学習が将来につながっていることを実感するためのステップアップ期間のようなものです。
職場体験を通じて、日常生活における主体性や積極性などを育むことを目的としています。
保護者としてのキャリア教育の実践
家庭でできるキャリア教育サポート
子どもの自己肯定感や安心感を育むことがとても大切です。
家庭で実践 3つのポイント
親ができる教育は、日頃のちょっとした会話や行動の中にもあります。小学生のうちから、たとえば次のようなことを少し意識して行ってみませんか。
好きなことが尊重される環境
キャリア教育において重要なポイントは、子どもの興味や好きなものを尊重することです。
勉強に直接関係しないテーマでも構いません。
子どもの興味を認め、サポートする姿勢を示すことが保護者として重要です。
これにより、子どもは自分の興味を追求する場を持つことができます。
また、子どもの考えや感覚を肯定することも重要です。
小学生の時期は、子どもが内から湧いてくる感覚や意思に自信を持てる機会を提供すること重要です。
これが、子どもの好奇心や意欲の育成につながります。
家庭での実践事例
仕事の話をしてみよう!
子どもにとってもっとも身近なキャリアは保護者の仕事です。
子どもは成長するにつれ、保護者が働いているから家庭にお金があり、そのお金でご飯を食べたり、物が買えるということに気づいていきます。
保護者が、自身の仕事について、具体的な仕事内容の話に始まり、仕事の自慢や不平・不満、仕事の社会的な意義、職業選択のきっかけや理由など、保護者が通ってきた道について、具体的に伝えてください。
子どもにとっては、一番身近にいる保護者が「どんな風にして大人になってたか」を知ることは、生き方の何よりの道しるべです。成功体験だけでなく、失敗や挫折の体験こそ、子どもの年齢に応じてわかりやすく、楽しく、話してあげてください。
日常の役割分担をお願いしよう!
家庭では、食器の片づけやお風呂掃除など、子どもの役割を決めましょう。日常生活の中で、子どもは自分のやるべきことを「いつ、」「どのようにすればよいのか」を理解するようになります。
子どもが自分の役割を持つことは、自己理解や自己管理能力、課題対応能力、プランニング能力を引き出すきっかけとなります。
役割を果たした都度、感謝を伝えることで、子どもの自己肯定感を高めましょう。また、自分の役割り以外のことを手伝ったり、家族と協力したりすることで、他者との関わりの大切さも実感できます。
キャリア教育は未来を生き抜くために必要な学び
キャリア教育のまとめ
- 変化の激しい社会で、自立して生きていくためにもキャリア教育は必要
- 小学校では身近なところで様々な経験を積んで、職業や社会の仕組みを学習
- キャリア・パスポートには、小学校から高校まで学んだり身につけたりしたことを記録可能
特に心身ともに成長が著しい小学生が、働くことの意味や人と社会の繋がりを身近に感じることは、これからさらに変化が激しくなっていくであろう未来の社会を生き抜くために、とても大きな力となります。
子どもの教育は3つの視点で
子どもには、なるべくたくさんの視点から学ぶ機会が必要です。- 系統的な学校教育 … 知識として身につきやすい学べる体験
- 体験から学ぶ教育 … 習い事、博物館、キャンプなどの体験
- 身近な人から学ぶ教育 … 見ているだけで学べるのが保護者の背中
キャリア教育は、難しいものではありません、
文部科学省の教育方針
小学校でのキャリア教育は、国が具体的なカリキュラムを定めているわけではなく、各自治体や学校によって取り組み内容はさまざまです。文部科学省では「小学校キャリア教育の手引き 改訂版」(2011年5月)の中で、低学年・中学年・高学年における具体的な教育方針を掲げていますので、ここでは、抜粋を紹介します。
低学年でのキャリア教育
好きなこといっぱいできる 学校って楽しいな
低学年では、自分の好きなこと、得意なこと、できることを増やし、様々な活動への興味・関心を高めながら意欲と自信を持って活動できるようにすることが大切です。
中学年でのキャリア教育
自分と 友だちと みんないっしょに
友達のよさを認め、協力して活動する中で、自分の持ち味や役割が自覚できるようにすることが大切です。高学年でのキャリア教育
挑戦する やりぬく 夢・希望を広げる
高学年では、苦手なことや初めて挑戦することに失敗を恐れず取り組み、そのことが集団の中で役立つ喜びや自分への自信につながるようにすることが大切です。友達のよさを認め、協力して活動する中で、自分の持ち味や役割が自覚できるようにすることが大切です。
子どもの教育