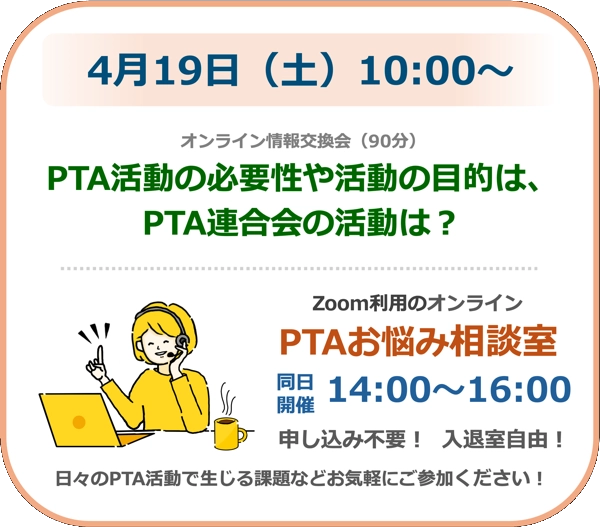子どものSOSサイン気づきのポイント、気づいた時の対応方法
子どものSOS 気づきと対応

子どものメンタルヘルス
子どものSOSサインに気づく
ストレスをためている、こころの健康状態が優れないときに、一般的によく出てくる「こころのSOSサイン」もあれば、一緒に生活する家族だからこそ気づきやすいサインもあります。
ここでは、ご家庭だから出てきやすいSOSサインをご紹介します。
「何だかこれまでと様子が異なる」「以前はこんなことはなかったのに・・・」など、SOSサインに気づくには日頃のコミュニケーションが大事です。
家族だからこそ気づきやすいSOSサイン
- 朝、起きられない。
- 睡眠のリズムがくずれている。
- 食欲がない、あるいは食べすぎる。
- 急激にやせたり太ったりする。
- (特に朝)頭痛や腹痛を訴える。
- 元気がない、顔色が悪い。
- 学校に行きたがらない、行かない。
- 無口になった、家族と話さなくなった。
- 一人で部屋にこもりがちになった。
- イライラしている、ちょっとしたことで怒りっぽくなった。
周囲の人たちにも様子を聞いてみましょう
もしかすると、いつも一緒にいるからこそ気づきにくいということもあるかもしれません。
近すぎて、当たり前になってしまうのでしょう。
また、家族に心配をかけまいとしているかもしれません。
そのような場合、家族以外の人がサインをキャッチすることもあるでしょう。
「前はすごく元気に挨拶してくれたのに、最近してくれないのよ、何かあったの?」
「最近、お友達と遊ばなくなったんじゃない?」といったかたちで、SOSサインを知らされることもあるでしょう。
ですから、子どもの友達、友達のご両親など、子どもを取り巻くネットワークと、日頃からコミュニケーションを深め、相談できる関係を築いていくことも大切です。
「自分を傷つける」というサイン
ストレスから自分を傷つける行為が、10代から20代を中心とした若い世代にみられます。
リストカット、たばこの火を押しつける、ピアス穴を過剰にあけるなどのほか、髪の毛を抜く抜毛症などもあります。
リストカットをしたからといって自殺したいと思っているとは限りません。
これらの行為には、自分の体を傷つけることで、精神的な苦痛を和らげようとする気持ちが隠れていることがあります。
自傷行為について
- 怒り、空虚感、寂しさ、劣等感などの感情が抑えられず、自分を傷つける。
- くりかえし行うことが多い。
- 次第に常習化する。
- 複数の方法や手段で行うこともある。
- 自尊心が低く、自己否定的なことが多い。
- 虐待が原因となる場合もある。
自傷行為を行う子どもに対して
- 自傷行為を責めない。
- なぜ行うのか、そんなことをして何になるのかなどと問い詰めない。
- 精神的ストレスから、自分を傷つける人もいることを伝える。
- 「自分を傷つけたいほど、つらいんだね」など、苦しい気持ちに寄り添う。
- 傷つけたくなったとき、いつでも話を聞く準備があることを伝える。
- 「そばにいる」「一緒に治していこう」と、支えになることを伝える。
自傷のすべてがこころの病気ではありませんが、中には、統合失調症、うつ病、摂食障害、境界性パーソナリティ障害、解離性同一性障害など、こころの病気が重なっていることがあります。
また自傷行為は自殺とは区別して考えることが必要ですが、継続して行われる場合には長期的に自殺につながってしまうことも少なくありません。自傷行為は、子どものこころがSOSを出している証拠です。
ゆっくりと話を聞きながら、こころの専門家に相談してみることをお勧めします
「消えてしまいたい」というサイン
一人で悩みを抱えてしまうと、思い詰め、自殺を考えることもあります。学校の友人関係の悩みだけなく、うつ病、統合失調症などの病気でも、自殺のリスクが高まります。次のような前兆となるサインが見受けられるかもしれません。
- 自殺をほのめかす、自殺について口にする。
- 消えたい、いなくなりたいと言う。
- 自分は生きている意味や価値がないと言う。
- 生まれてこなければよかったと言う。
- 周りに迷惑をかけていると自分を責める。
- 自暴自棄になる。
- 身の回りのものを片づけたり、人にあげたりする。
- 薬やアルコールを乱用する。
このようなサインに気づいたら、必ず声をかけ、話を聞きましょう。
「バカなことを言うな」「何を考えてるんだ」などの言葉は、子どもをますます追い詰めてしまいます。
「心配している、大切に思っている」というあなたの気持ちを伝えること、「消えてしまいたいほど、つらい」という子どもの気持ちを受け止めることが大切です。
自殺のリスクが感じられるときは、一人にせず、近くで見守りましょう。
また、自殺のリスクが切迫していると感じるのであれば、速やかに専門家に相談し、どのように対応すればよいかアドバイスをもらうべきでしょう。
子どものSOSに気づいたら
気づいたときの対応法
話を聴く姿勢
- 話を聞くことに集中する(何かをやりながら片手間に聞くことはしない)。
- 子どもの気持ちに共感し、受容する。
- 子どもがどのように感じているか、子どもの気持ちで理解する。
- 親としての意見や、思いを押しつけない
話を聞くときの具体的なノウハウ
- 子どもが話した内容を、時々くりかえす。
- とくに「つらい」「悲しい」「不安」など感情を表す言葉は伝え返す。「つらいのね」など。
- 答えが「イエス」「ノー」にならないよう、できるだけ「How」で聞く。
- 言葉で伝えきれない場合には、紙に書いてもらう。
- これまでどんなふうに困難に対処してきたか聞く。
聞いた話を活かす
- 話したことの記録(メモ)をとっておく。
- 必要に応じて、スクールカウンセラー、養護教諭、教職員、専門家などに相談する。
- 子どもとじっくり話し、本人が納得したうえで受診を勧める。
聞いた内容によっては、「このことは先生に伝えて相談したほうがよいことだから~」と、説明してから第三者に伝えるようにしましょう。
本人が隠したいと思うことはできるだけ秘密にするけれど、健康や安全に関わることについては秘密にできないこともあるということを伝えましょう。
自分や家族を責めない
子どもの健康状態が気になるときは、ご家族にとって大変なこころの負担です。
ときには、自分を見失ってしまうこともあるでしょう。
「子どもが病気になったのは自分のせいなんだ」と自分を責めたり、場合によっては夫婦で互いに責めあうようなこともあるかもしれません。
そのことから、子どものほうでも「自分が悪いから親が困っている」と、自責感を強めてしまうことにもなりかねません。
子どもの不調は誰のせいでもありません。
原因探しにやっきになって、「育て方が悪かった」と自分を責めたり、家族内で責めあったりして、家族の仲が悪くなることは、子どものストレスをさらに増やすことになるでしょう。
つらいとき、大変なときだからこそ、家族で支えあい、互いに協力しあうことが大切です。
困った時の相談先(保護者)
こころの相談窓口
こころの健康相談統一ダイヤル
また、全国共通の「こころの健康相談統一ダイヤル」があり、電話をかけると、地域の公的な電話相談窓口につながります。こころの問題だけでなく、様々な相談窓口を掲載している「いきる・ささえる相談窓口」などがあります。
Tel. 0570-064-556
地域の公的な電話相談窓口についての詳細は、
厚生労働省 こころの健康相談統一ダイヤルについて ≫
いのち支える相談窓口
全国の自治体や厚生労働省が案内するこころと体の健康・病気に関する様々な悩みを受け付ける公的な相談窓口がまとめてあり、都道府県別に検索できます。 自殺総合対策推進センター ≫親子のための相談LINE
子育てや親子関係について悩んだときに、子ども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口です。
匿名(LINE上のアイコンとニックネーム)でも相談ができます。相談内容の秘密は守られます。
親子のための相談LINEについての詳細は、
こども家庭庁「親子のための相談LINE」について ≫
身近にある地域の相談窓口
保健所、保健センターなど
不眠、うつなど、こころの病気に関する不安や悩みほか、家庭内暴力やひきこもり、不登校など思春期の問題に関する相談、アルコール・薬物などの依存症に関する相談などを受け付けています。
医師などのこころの専門家に相談することもできます。
最寄りの保健所、保健センターの相談窓口を検索できます。
厚生労働省 保健所管轄区域案内 ≫
精神保健福祉センター
こころの健康相談から精神医療に関わる相談、アルコール・薬物乱用、思春期・青年期の相談などに応じています。
こころの病気に関する不安があるとき、医療が必要かどうかも相談できます。近隣の医療機関などを紹介してもらうことも可能です。
最寄りの精神保健福祉センターの相談窓口を検索できます。
厚生労働省 全国の精神保健福祉センター ≫
いじめや不登校、ひきこもりなどの相談窓口
児童相談所、児童相談センター、児童家庭支援センターなど
18歳未満の子どもやそのご家族を対象として、子育てやしつけの悩み、発達障害、子どもの行動上の問題などについて相談することができます。教育センター
高校生相当の年齢までの子どもやその保護者、学校関係者を対象として、不登校やいじめ、発達障害など、教育場面での悩みを中心に相談することができます。都道府県や市区町村に設置されています。ひきこもり地域支援センター
ひきこもりの本人やご家族からの相談を受け付け、必要に応じて関係機関と連携した支援を行っています。
全国には、ひきこもりに関するさまざまな支援機関・相談窓口があります。
なかでも、「ひきこもり地域支援センター」では、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ支援コーディネーターが中心となって、相談支援や、地域における関係機関と連携した支援を行っています。
2021年4月現在すべての都道府県・指定都市に設置されています。
全国のひきこもり地域支援センターの一覧 ひきこもりVOICE STATION
厚生労働省 ひきこもり地域支援センター ≫
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。発達障害児(者)とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障害児(者)とその家族からのさまざまな相談に応じ、指導と助言を行っています。
ただし、人口規模、面積、交通アクセス、既存の地域資源の有無や自治体内の発達障害者支援体制の整備状況などによって、各センターの事業内容には地域性があります。詳しい事業内容については、お住まいになっている地域の発達障害者支援センターに問い合わせてください。
全国地図から最寄りの発達障害者支援センターの相談窓口を検索できます。
国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害者支援センター・一覧 ≫
児童相談所・児童相談センター
児童相談所
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。原則18歳未満の子どもに関する相談や通告について、子ども本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。
児童相談所は、すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
児童相談センター
児童福祉法施行規則では、都道府県知事は設置した児童相談所のうち一つを、他の児童相談所を援助し、その連絡を図るために、中央児童相談所に指定することができることとされています。東京都の場合には、児童相談センターを中央児童相談所として位置づけています。
相談例
- 保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子どもが家庭で生活できなくなった。
- 虐待など子どもの人権にかかわる問題がある。
- わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配である。
- 知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向がある。
- 家出、盗み、乱暴、性的いたずら、薬物の習慣などがある。
- 里親として家庭で子どもを育てたい。
児童家庭支援センター
子ども、家庭、地域住民等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行う施設です。また、児童相談所、児童福祉施設など、関係する機関の連絡調整も行います。児童相談所を補完するものとして、児童福祉施設等に設置されています。利用料は無料で、電話や来所などにより、直接相談をすることができます。
- 地域の子どもに関する様々な問題について、家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに対して、必要な助言を行います。
- 市町村からの依頼に応じて、乳幼児健診、家庭訪問事業、発達障害児の支援教室への職員派遣、教員研修への講師派遣などを行っています。
- 児童相談所に定期的に通所することが地理的に困難な子どもや、逆に定期的な訪問が困難な子ども、施設を退所後間もない家庭について、児童相談所より委託され相談援助を行っています。
- 里親及びファミリーホームからの相談に応じるなど、必要な支援を行います。
- 各連携機関の会議や連絡会に参加し、情報交換や連絡調整を行う他、地域における要保護児童のケースカンファレンスや情報交換などを行っています。
児童家庭支援センターは、地域とのつながりを最大限に活かした子育て支援などを担い、養育不安等に対応する、児童虐待の発生予防的な対応を担う機関です。
児童福祉法には「児童家庭支援センター」という名称がありますが、「子ども家庭センター」という文言の記載でありません。子ども家庭センターと児童家庭支援センターは同じものとは言えませんが、地域によっては「子ども家庭センター」という名称で児童家庭支援センターを指す場合もあります。
困った時の相談先(子ども)
24時間子どもSOSダイヤル(文部科学省)
子どもたちが全国どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでもいじめやその他のSOSをより簡単に相談することができるよう、全都道府県及び指定都市教育委員会で実施しています。
下記のダイヤルに電話すれば、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続します。
Tel. 0120-078310
子どもの人権110番(法務省)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
Tel. 0120-007-110
このような悩みがあったら、迷わず電話してください。「まわりでこんなことで困っている人がいる」という相談でもいいです。
児童虐待防止
児童虐待かも ・・・ と思ったら、すぐに電話を!
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。
子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。
児童虐待の定義
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなどネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど心理的虐待
言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、兄弟に虐待行為を行うなど児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
- 虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
- 「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけるとお近くの児童相談所につながります。
- 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
関連情報