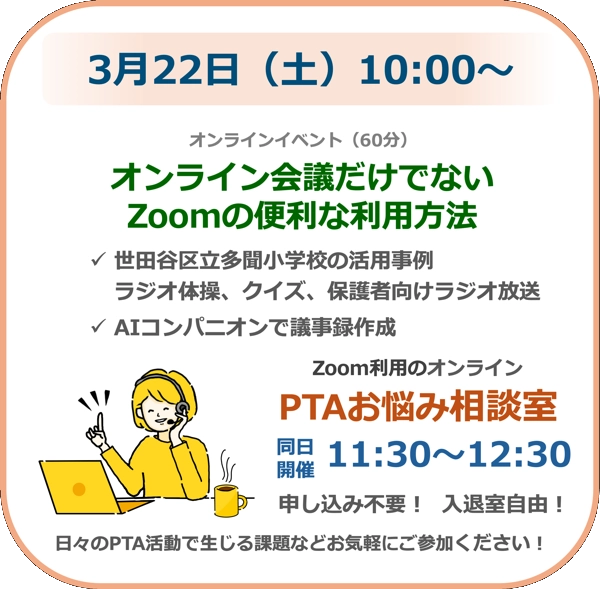定額働かせ放題とも揶揄される
公立学校教員を対象にした給特法

給特法とは
給特法の正式名称は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」で、日本における公立学校の教育職員の給与や労働条件を定めた法律です。
校長、副校長、教頭を除く教育職員には、時間外勤務手当や休日勤務手当などの残業手当を支給しない代わりに、教職調整額を支給しなければならないことになっています。
教育調整額とは、教育職員の勤務時間の長短を問わず、勤務時間外の職務に対する評価も含んだ対価として、給料月額4%が支払われています。
給特法成立の経緯
戦後、公務員にも、一般労働者と同様に労働基準法が適用されていましたが、当時の大蔵省などを中心に、公務員は勤務部署や職務などによって拘束時間が大きく異なるという問題が指摘されるようになりました。
1948年の公務員の給与制度改革により、1週間の拘束時間の長短に応じた給与を支給することとなりましたが、教員の給与については、勤務の特殊性から、1週48時間以上勤務するものとして、一般公務員より一割程度高い俸給が支給されることになりました。
併せて、教員に対しては超過勤務手当は支給されないこととされ、文部省では、超過勤務を命じないよう指導してきました。
その背景には、教員の仕事の特殊性があり、具体的には、自身の指導力を高めるため勤務時間終了後に自主研修会を開いたり、保護者の退勤を待って個別の面談や児童生徒の預かりをしたりするなど、勤務時間を一律に定めることが困難で、勤怠管理も難しい側面があったとされています。
当時の公立学校における教員の労務管理上の課題として2つの側面がありました。
- 労働基準法に照らして、時間外勤務手当を支給するという考え方を適用
- 教育公務員特例法に照らして、教育公務員に時間外手当を支給しないこと
… 国立学校の教育公務員給与の考え方に準拠するということ
その後、教員の超過勤務が大きな問題となるにしたがって、教員の給与と勤務時間の関係も議論となり、当時の文部省は、1966年に全国的な教員勤務状況調査を実施しています。その調査結果を踏まえ、教員の時間外労働は月平均で約8時間とし、1971年に国公立学校の教員に対し、俸給月額の4%相当の「教職調整額」を支給する法律を制定、翌年から施行されています。
施行時の名称は「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が制定され、2004年に現在の名称でに改められました。
教員の勤務態様の特殊性
教員は、教員固有の勤務態様により勤務時間の管理が困難、一般行政職と同じような勤務時間管理はなじまない。- 教修学旅行や遠足など、学校外の教育活動
- 教家庭訪問や学校外の自己研修など、教員個人での活動
- 教夏休み等の長期の学校休業期間
勤務態様の特殊性を踏まえた処遇
教員の勤務態様の特殊性を踏まえ、教員については、勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇として、
- 時間外勤務手当を支給しないこと
- 原則として時間外勤務を命じないこと
- 時間外勤務を命じる場合は、特定の業務に限定(いわゆる超勤4項目)
- 時間外勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給。
- 教職調整額を本給と見なして、本給を基礎とする手当等(期末・勤勉手当、地域手当、へき地手当、退職手当等)の算定の基礎となています。
- 「4パーセント」は1961年の勤務状況調査の結果を踏まえて、超勤4項目にあたる月8時間分として算定
- 生徒の実習に関する業務
- 学校行事に関する業務
- 教職員会議に関する業務
- 非常災害等のやむを得ない場合の業務
給特法が継続する法的根拠
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の第三条第2項
教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
これに基づき、教員に対して残業代や休日勤務手当などの超過勤務手当は支給されず、労働基準法第37条の適用から除外されています。その代わりとして、給与月額の4%が教職調整額として支給されています。
2024年の中教審答申では、給特法は継続、教員に時間外勤務手当を支給しないことが改めて確認されています。
給特法の対象者
この法律の対象者は、公立の義務教育諸学校等の教育職員で、私立学校の教育職員はこの法律の適用外です。
- 義務教育諸学校とは、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園
- 教育職員とは、義務教育諸学校の校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、用語助教諭、講師、実習助手及び寄宿指導教員
令和の給特法改正
教師の業務は長時間化しており、近年の実態は極めて深刻であり、持続可能な学校教育の中で教育成果を維持し、向上させるためには、教師のこれまでの働き方を見直し、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることが急務として、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が制定され、給特法改正が行われました。
一年単位の変形労働時間制の適用(休日のまとめ取り等)
- 夏休み等児童生徒の長期休業期間の教師の業務の時間は、学期中よりも短くなる傾向があり、休日のまとめ取りのように集中して休日を確保することを可能にする。
- 公立学校の教師については、地方公共団体の判断により、一年単位の変形労働時間制の適用することが可能になる。
業務量の適切な管理等に関する指針の策定
- 教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間を「在校等時間」と定義する。
- 超勤4項目以外の業務を行う時間も含める。
- 1ヶ月の時間外在校等時間45時間以内、1年間の時間外在校等時間について、360時間以内と定める。
なぜ、給特法のさらなる改正が検討されているのか
法制定当時の1966年ごろには月8時間だったとされる時間外勤務は、現状との乖離が大きくなっています。
「超勤4項目以外は時間外勤務を命じない」という原則が形骸化したことなど、さまざまな要因で教員の多忙化が進み、いわゆる「過労死ライン」を超える長時間勤務を余儀なくされる事例などもあり社会問題となっています。
文部科学省の調査(2016年)では、1日あたりの勤務時間が小学校で、11時間15分、中学校で11時間32分とされています。この数値を月単位に換算すると、70時間程度の時間外勤務となっています。
また、教師不足に関する実態調査(2022年)では、全国の多くの自治体で教員不足が明らかになり、教員の休職・退職の増加、教員志望者の減少などが深刻となっています。
超勤4項目
文科省による超勤4項目の運用方針
給特法制定時には、超勤4項目の時間外勤務に対して、以下のような厳格な運用方針が示されていました。法の精神からすれば、労働基準法の適用を考えると、この運用方針は重要なものです。
- 長時間の時間外勤務はさせないようにし、やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること。
- 日曜日又は休日等に勤務させる必要がある場合には、代休措置を講じて週一日の休日の確保に努めるようにすること。
- 時間外勤務を命ずる場合は、学校の運営が円滑に行われるよう関係職員の繁忙の度合い、健康状態を勘案し、その意向を十分尊重して行うようにすることと。
文科省による超勤4項目の解釈
部活動や家庭訪問など超勤4項目に該当しない業務は、本来であれば、教員に命じることのできない時間外勤務であり、教員は拒否することが可能ですが、文部科学省では、教員の職務について以下のように言及しています。このため、勤務時間外で超勤4項目に該当しないような教職員の自発的行為に対しては、公費支給はなじまない。また、公務遂行性が無いことから公務災害補償の対象とならないため、別途、必要に応じて事故等に備えた保険が必要。
文科省による労働時間の定義
2021年の文部科学省の「ガイドラインの運用に係るQ&A」では、校務であったとしても、使用者(校長)の指示がない場合は、教員の「自発的行為」としています。厚生労働省の労働時間の定義は、明示又は黙示の指示により、使用者の指揮命令下に置かれ、労働者が業務に従事する時間とされています。使用者からの指示に基づかず自発的な判断により行われているのでしょうか?
給特法を考える
国は明確に教員の業務は特殊であるとしています。教育職員の働き方改革が進んでいない現状のまま、もし、勤務態様の特殊性がないとして一般公務員と同様、時間外勤務手当を支払うことになると、膨大な予算が必要になることが想像されます。
教育職員の業務は特殊なのかという点に関しては、私たち保護者の立場では意見がわかれることもあります。
仕事の対象が子どもであり、教育し育てるという観点においては、教員は特殊な仕事だと思います。
一方で、「教材準備」「授業」「学級や学年の事務」「児童生徒の指導」「部活動指導」「校外や地域対応」など業務の仕分けは可能であり、業務別に時間外勤務の管理を行うことは可能だと考えます。
業務別に時間外勤務の管理すると同時に、学校や教師が担う業務に係る課題についての社会全体での取り組みも必要であり、教職調整額だけなくさまざまな視点での対策が必要となります。
給特法は、教育職員の待遇確保のために定められた法律ですが、かつてよりも在校時間が減少しているものの依然として長時間勤務をしている教育職員が多いにも関わらず、正当な対価が支払われていない点が問題となっています。
また、教育職員が現在行っている時間外勤務には、「超勤4項目」に関わる業務もあればそれに該当しない業務もあり、判別が難しい部分もあります。
生徒指導案件や保護者への対応事案、PTAなど任意団体の事務局など、校長の推薦や承認を得ている場合もあり、教育職員個人が断ることが難しい構造も指摘されています。
教育職員が「自主的で自律的な業務」であるとしっかり線引きできない業務も少なくない中、給特法の仕組みが、現在の教育職員の勤務実態とあっていない、正しく運用されていないとの指摘もあります。
管理が進みすぎると、自発的・創造的に働くことへのモチベーション低下も懸念されます。給特法での教育職員の職務の特殊性は、時間外を含め自主的に働くものであるから厳格な時間管理はなじまないとしています。
教育職員が専門性をたかめるため、教材研究として価値のある博物館や美術館に行くことは、業務としての教材研究かという議論もあります。
民間企業の社員も自らのスキル向上のため、同様の行動を行う場合があり、仕事をしている人間であれば、日常の何らかの行動が仕事のヒントなどにつながることも少なくないと思います。
一つの考え方として、研究会や研修旅行、出張などは別として、業務というのは、基本的に職場内で行うものではないでしょうか?
教育職員あれば、授業の教材、進め方など授業に直接関係のあることや児童生徒の指導など、子どもたちに直接関係のあることは、明らかな業務です。
教員の職務は自発性や創造性が求められる部分が大きいため、働き方の実態調査や、適切な評価を行う仕組みづくりが必要であり、業務としての教材研究の議論には、給特法の見直しなども必要と考えます。
給特法では、部活指導など。時間外勤務を自発的なものであるとして労働と認めない運用であるとの議論もあります。
実際の学校職場では、明示・黙示の指示があり、2つのジレンマがあるとされています。
- 自分が対応しないと子どもの学びに対する悪影響が出ること
- 他の教員が穴埋めすることになるという申し訳なさ
給特法の廃止を主張の根拠としては、給特法が廃止されて労働基準法が適用され、民間企業などと同様に時間外手当が支払われるようになれば、業務量に歯止めがかかり、問題が解消されるという意見があります。
一方で、給特法が適用されていない私立学校にも無報酬時間外勤務の問題はあり、給特法の廃止で問題が解決するとは限らないとの主張もあります。
給特法を見直しをして教職調整額の引き上げをするのであれば、次のような対策が必要と考えます。
- 給特法を正しく運用して超勤4項目以外の残業は命じない。
- 勤務実態などを踏まえ、教職調整額を適切な額に引き上げる。
給特法の趣旨と、現場の運用実態とは大きく乖離し、4項目以外の残業(部活動など)が自主的活動であるとして労働時間とすら扱われず放置されているのが実状です。給特法が厳格に運用されることにより、長時間労働の改善点はより明白なると考えられます。
給特法の正しい運用にあたり、学校長や教育委員会など管理者に対する罰則規定を追加するのが良いとの指摘もありますが、教育現場の実態を踏まえると難しいとの指摘もあります。 しかしながら、給特法の適正な運用がないまま、現状の勤務に見合った教職調整額を支給するのは、財政上の問題となります。
給特法を廃止したら、教員の長時間勤務が改善されず、教員給与が下がるか、残業代が支払われない、という事態が起きるのではという説もありますが、この説は、労働基準法の労働時間規制が実現しないこと、人事委員会の勧告による是正の機会もある地方公務員の給与引き下げが前提となります。
もし、給特法が廃止された場合は、労基法が適用され、残業抑制の仕組み働くと考えられます。労基法の労働時間規制は、時短という目的であり、教員増・業務削減を実効化するための手段であると考えます。
学校で働く教育職員以外(事務職員や現業職員等)は、給特法の適用対象外となっており、残業には、原則通り労基法が定める36協定が必要となります。
日教組の学校現場の働き方改革に関する意識調査(2022年)によると、88.1%の学校で36協定が締結されているとされています。また、公立以外の私学や国立付属の教員、大学教員は、労基法が適用されています。
職務の特殊性は、医師などを含め多くの仕事に存在しますが、労基法の労働時間規制は基本的に適用されています。医療業界や物流業界には2024年問題が話題になりましたが、給特法の適用対象である教育職員にはこうした問題は起きていません。
教員の時間外勤務手当
手当支給をしない3つの理由 … 文科省
国立学校や私立学校では時間外勤務手当の支払いがなされており、公立学校も対象とすべきであるとの指摘もある中で、文科省では以下のように述べています。
この点については、職務の特殊性は、国立学校や私立学校の教師にも共通的な性質があるが、
- 公立学校の教師は、地方公務員として給与等の勤務条件は条例によって定められているのに対し、国立・私立学校の教師は非公務員であり、給与等の勤務条件は私的契約によって決まるという指勤務条件等の設定方法の違いは大きいこと
- 公立の小・中学校等は、域内の子供たちを受け入れて教育の機会を保障しており*1、在籍する児童生徒等の抱える課題が多様であることなど、国立・私立学校に比して、公立の小中学校等においては相対的に多様性の高い児童生徒集団*2となり、より臨機応変に対応する必要性が高いこと
- 公立学校の教師は、定期的に学校を跨いだ人事異動が存在することにより、特に社会的・経済的背景が異なる地域・学校への異動があった場合等においては、児童生徒への理解を深め、その地域・学校の状況に応じて、より良い指導を行ための準備を行う必要があるが、それをどのように、どの程度まで行うかについて個々の教師の裁量によるところが大きいこと
など、職務の特殊性が実際の具体的な業務への対応として発現する際の有り様は、公立学校の教師と国立・私立学校の教師とで差異が存在する。
- 1.一方、国立学校や私立学校は、教育研究方針や建学の精神等に基づく特色ある教育を行うことを掲げており、その教育方針を踏まえて入学を希望する子供たちが選抜等を経て入学する教育機関であるという性格を有している。
- 2.中学校の生徒1,000人当たりの公立学校、私立学校、国立学校のデータは、以下のとおり。なお、小学校や高等学校においても、おおむね同様の傾向が見られる。
| 公立 | 私立 | 国立 | |
| 特別支援学級に在籍する生徒数 | 34人 | 0.4人 | 3.8人 |
| 通級指導を受けている生徒数 | 9.2人 | 0.1人 | 0.3人 |
| 不登校生徒数 | 62.7人 | 29人 | 28.9人 |
| 外国人生徒数 | 9.8人 | 5.8人 | 1.7人 |
- 通級指導を受けている生徒数のみ2021年度、他は2022年度
国立と公立の教育職員の勤務条件設定における差異
- 国立学校の法人化に伴い、2004年度以降じゃ国立学校準拠制を廃止し、各都道府県等が教員の職務と責任の特殊性に基づき条例で決定(教育公務員特例法第13条)
- 教職一般の公務員2003年度以前は、公立学校教員の給与の種類及び額は、国立学校教員の給与の種類及び額を基準として 各都道府県等が決定。
- 国は、人材確保法の趣旨を踏まえた教職員給与費が確実に支給されるよう、義務教育費国庫負担制度により必要な財源を保障。(義務教育費国庫負担法第2条)
職務の特殊性に関する疑問
勤務条件等の設定方法の違い
公立の教育職員を除く一般の公務員と民間企業の従業員で考えた場合、勤務条件等の設定方法には、大きな違いがあります。
国立学校や私立学校と比べた場合の公立学校との違いを、どう考えるべきか?
より臨機応変に対応する必要性が高い
国公私立学校いずれも、同じ学習指導要領に則って教育活動を行っていますが、相違点として、前期の*1、*2が例示されています。実際の勤務時間で考えると、教育活動にあてる時間が多く、相違点としての多様性対応の時間は、あまり多くないのではないか?
また、国立学校や私立学校でも公立学校同様に、いじめや不登校などの課題は存在し、重大事案も発生しています。
教育職員は、校種に関わらず、臨機応変に対応しているのではないか?
社会的・経済的背景が異なる地域・学校への異動
同一の自治体内であっても保護者、地域の状況が異なる学校もあります。国立学校や私立学校では同種の移動はありませんが、国立学校は、教育実習生に対する指導や研究的側面が、私立学校は、少子化の中、選ばれる学校としての教育などがあり、各学校の状況に応じた教育が行われています。
教育職員は、より良い指導を行ための準備を、校種に関わらず個々の裁量をもって行っているのではないか?
学校や教師に関する課題