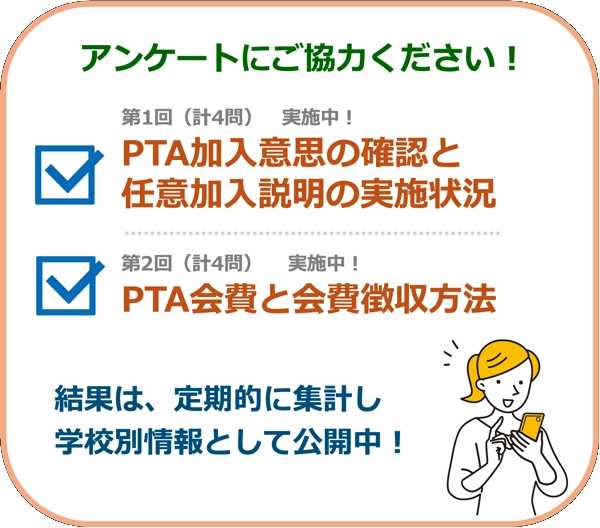持続可能な開発目標(SDGs)とは

SDGsは、子どもの権利と強く関連しており、この目標を達成することは、子どもに関連するさまざまな課題を解決することにもつながります。
保護者の皆様と共に、SDGsが大切にしていることや、各目標の内容について理解を深めていきたいと思います。
SDGsとは?
持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
持続可能な開発目標(SDGs)

- 普遍性 先進国を含め、全ての国が行動
- 包摂性 人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」
- 参画型 全てのステークホルダーが役割を
- 統合性 社会・経済・環境に統合的に取り組む
- 透明性 定期的にフォローアップ
SDGs に関するキーワード
持続可能な開発
持続可能な開発とは、「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」と定義づけられ、人々と地球のために包摂的、持続可能な、レジリエント、すなわち強靭な未来を築くことが求められています。
この目的を達成するために三つの核心的要素、すなわち経済成長、社会的包摂、環境保全を個人と社会の福祉のために必要な要因としてその調和を図ることが不可欠であるとされています。
SDGsが目指すこと
SDGs策定以前から、社会、環境、経済などの問題に対する取り組みが行われていましたが、SDGsの採択により、それらの問題に関する目標を一つにまとめられました。
- 経済発展だけにとどまらず、環境や社会が抱える問題にバランスよく取り組むこと
- 世代を超えたすべての国、すべての地域の人々が、誰一人取り残されることなく、尊重される社会を目指すこと
- 貧困を終わらせ、地球環境を守り、すべての人々が平和と豊かさを享受できる世界を実現すること
人権
人権(英:human rights)とは、人種や性別、国籍、民族、言語、宗教などにかかわらず、すべての人間に固有の権利を指し、誰もが生まれながらにして持っている、人間らしく、自分らしく生きることのできる権利のことです。
人権には、人種・性別・身分などの区別に関係なく(普遍性)、人間であることにより当然に有し(固有性)、原則として公権力に侵されない(不可侵性)という特徴があります。人権は、大別すると「自由権」「参政権」「社会権」の三つに分けられます。
参加
参加とは、目的をもって集まりに加わったり、行動をともにすることを指します。
参加を通して自分の考えを意見として表明したり、その意見が聴かれることは、すべての人の権利です。
SDGsへの参加の具体例
- 政府機関やNPO団体などを支援、ボランティア活動に参加する
- 地産地消を心がける
- 節電や節水、エコバッグやマイボトルを持ち歩く
- 家事や育児の分担を行う
- フリマアプリを利用して不用品を売却する
- 車での移動はせずに自転車や公共交通機関を活用する
- 情報発信を行う
貧困
貧困にはさまざまな定義がありますが、食べ物や、健康な体、学校に行くことなど、生きていくのに必要なものが十分でない状態を指します。
- 国際貧困ライン:世界銀行が定める1日1.9米ドル未満で生活する人のこと
- 絶対的貧困:人間としての最低限の生活水準が満たされていない状態
- 相対的貧困:ある国や地域社会の水準と比較して大多数よりも貧しい状態
ジェンダー
男性や女性といった生物学的な性差とは異なり、たとえば、女性らしさや、男性らしさのような、ある社会や文化のなかで作り上げられた男性像、女性像を指します。
SDGsでは、ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図ることを目標としています。
- 女性や女児に対するあらゆる形態の差別や暴力の撤廃
- 未成年の早期結婚や強制結婚、女性器切除などの有害な慣行の廃止
- 未無報酬の育児・介護や家事労働の評価
- 未人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性および女子に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力の排除
衡平(こうへい)
衡平は、違いを前提として、その違いに応じた異なる対応を行うことで、みんながそれぞれの権利を平等に得られるようにすることです。
衡平は、世界がより発展し、平和で公正(かたよらず、正義があること)な場所になるために大事な考え方です。
- 女世界がより発展し、平和で公正な場所になるために大事な考え方です。
- 人種や性別、階級などを理由に差別されることのない平等な世界を目指します。
- 安全かつ秩序のある移住の促進や、立場的に弱くなることの多い開発途上国の発言力拡大にも取り組む内容です。
衡平と公平の違い
衡平(equity)と公平(equality)は、どちらも「こうへい」と表記されますが、意味が異なりま、公平は人々に対して同一待遇を施すことを意味します。UNESCO
UNESCOは、United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:UNESCOの略で、国際連合教育科学文化機関と訳されています。第二次世界大戦後の1946年にユネスコ憲章の発効に基づき国際機関として設立され、教育・科学・文化、コミュニケーションを通じて国際理解や国際協力を推進し、人びとの交流を通した国際平和と人類の福祉を促進しています。
ユネスコ憲章の前文では、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」とされています。
我が国においては、1952年に制定された「ユネスコ活動に関する法律」に基づき、文部科学省に日本ユネスコ国内委員会が設けられています。また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において、教育委員会の事務の一つとして、ユネスコ活動に関することが明記されています。
ユネスコ本部には、教育、自然科学、人文社会科学、情報・コミュニケーション、文化に関する局があり、このうち教育局において、ユネスコスクール及びESD(持続可能な開発のための教育)を担当しています。
SDGs 17のゴール
17のゴールは、①貧困や飢餓、教育など未だに解決を見ない社会面の開発アジェンダ、②エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消などすべての国が持続可能な形で経済成長を目指す経済アジェンダ、そして③地球環境や気候変動など地球規模で取り組むべき環境アジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示しています。
SDGsは、これら社会、経済、環境の3側面から捉えることのできる17のゴールを、統合的に解決しながら持続可能なよりよい未来を築くことを目標としています。
1.貧困あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる |
2.飢餓飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する |
3.保健あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する |
4.教育すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する |
5.ジェンダージェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う |
6.水・衛生すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する |
7.エネルギーすべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する |
8.経済成長と雇用包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する |
9.インフラ、産業化、イノベーション強靭(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る |
10.不平等国内及び各国家間の不平等を是正する |
11.持続可能な都市包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する |
12.持続可能な消費と生産持続可能な消費生産形態を確保する |
13.気候変動気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる |
14.海洋資源持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する |
15.陸上資源陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する |
16.平和持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する |
17.実施手段持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する |
SDGs達成に向けた国際協力への取組例
3.保健 健康的な生活の確保
4.教育 質の高い教育をみんなに
5.女性 ジェンダー平等と女性のエンパワーメント
11.防災
14.海洋環境
5つの「P」で考えるSDGs
「5つのP」とはSDGs上位概念であり、「人間(People)」「地球(Planet)」「繁栄(Prosperity)」「平和(Peace)」「パートナーシップ(Partnership)」という5つの性質の頭文字を取ったものです。
1. People
我々は、あらゆる形態及び側面において貧困と飢餓に終止符を打ち、すべての人間が尊厳と平等の下に、そして健康な環境の下に、その持てる潜在能力を発揮することができることを確保することを決意する。2. Prosperity
我々は、地球が現在及び将来の世代の需要を支えることができるように、持続可能な消費及び生産、天然資源の持続可能な管理並びに気候変動に関する緊急の行動をとることを含めて、地球を破壊から守ることを決意する。3. Planet
我々は、すべての人間が豊かで満たされた生活を享受することができること、また、経済的、社会的及び技術的な進歩が自然との調和のうちに生じることを確保することを決意する。4. Peace
我々は、恐怖及び暴力から自由であり、平和的、公正かつ包摂的な社会を育んでいくことを決意する。平和なくしては持続可能な開発はあり得ず、持続可能な開発なくして平和もあり得ない。5. Partnership
我々は、強化された地球規模の連帯の精神に基づき、最も貧しく最も脆弱な人々の必要に特別の焦点をあて、全ての国、全てのステークホルダー及び全ての人の参加を得て、再活性化された「持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップ」を通じてこのアジェンダを実施するに必要とされる手段を動員することを決意する。SDGsアクションプラン
「5つのP」はSDGsの上位概念であるため、そのまま個人や組織の具体的な行動にひもづけるものではなく、各国の政府機関や国際機関の文書でよく用いられます。「日本政府も「5つのP」と紐付けて日本特有の重点事項を整理し、その重点事項に各政府機関の具体的な予算を紐付けとして「SDGsアクションプラン」の策定を通じて行い、その内容を毎年発表しています。
個人や団体が「5つのP」を用いる際には、政府が整理した「SDGsアクションプラン」の内容と自分たちの行動を紐付けるることが有効であるとされ、行動の成果が出やすくなったり、他者と連携しやすくなると考えられています。 2024年の「SDGsアクションプラン」には、605の事業(施策)が掲載されています。
以下は、SDGs推進本部による「SDGsアクションプラン 2024」の一例です。
こどもの貧困対策(こども家庭庁)
- 貧困の連鎖を断ち切るため、全てのこどもが夢や希望を持てる社会の実現を目指し、親の妊娠・出産期からこどもの社会的自立までの切れ目のない支援体制を構築するとともに、支援が届いていない又は届きにくいこども・家庭を早期に発見して、こどものことを第一に考えた支援を包括的かつ総合的に講じていく。その際、地域の実情を踏まえた地方公共団体による取組の充実を図る。
- こどもの未来応援基金を通じたこどもに寄り添った活動を実施する民間団体への支援、支援を実施したい民間企業と支援を必要とする民間団体のマッチング等、「こどもの未来応援国民運動」を推進する。
保育所やこども園に対する施策(こども家庭庁)
こどもたちへの質の高い教育・保育の保障に向けて、保育所及び幼保連携型認定こども園における保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の着実な実施を進める。児童虐待防止対策・社会的養育の推進(こども家庭庁)
- 児童福祉司等の確実な増員・ソーシャルワークなどの専門性の強化や処遇改善、医師、弁護士、警察OBの配置促進など児童相談所の体制強化やこども家庭センターの設置促進・機能強化など市町村における子育て家庭への支援の充実・強化を図る。
- 児童相談所と関係機関間の連携を強化する。
- 委託先を含む一時保護の受け皿確保並びに一時保護施設の環境整備及び職員体制を強化する。
- 児童相談所の設置を目指す中核市等への児童相談所設置を促進する。
- 一時保護時の司法審査を導入する。
- 児童相談所等における業務のICT化を推進する。
- 特別養子縁組・里親養育への支援の拡充、職員配置基準の強化を含む児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の更なる推進、施設退所後の自立支援の強化など官民の多機関・多職種の連携の強化の下での社会的養育を充実・強化する。
子供の性被害防止対策の推進(こども家庭庁)
200年5月に犯罪対策閣僚会議で決定された「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」に基づき、関係府省庁等が相互に緊密に連携し、子供の性被害防止に係る対策を推進中であり、引き続き当該分野での取り組みを行う。
生命(いのち)の安全教育推進(文部科学省)
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、子供たちを性暴力の加害者・被害者・傍観者にしないための「生命(いのち)の安全教育」の教材や指導の手引きを活用したモデル事業や指導事例の収集等を実施するとともに、生命(いのち)の安全教育全国フォーラムを開催し、生命(いのち)の安全教育の全国展開の加速化を図る。
特別なニーズに対応した教育の推進(文部科学省)
共生社会の形成に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行う。また、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう連続性のある多様な学びの場の整備を行う。
体罰禁止の徹底(文部科学省)
体罰禁止の徹底を図るため、体罰の実態調査を実施するとともに、各都道府県教育委員会等の生徒指導担当者向けの会議等において、懲戒と体罰の区別、体罰防止に関する取組についての通知の内容を周知する。
いじめ対策の推進(文部科学省/こども家庭庁)
いじめの未然防止、早期発見・早期対応等を実現するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置充実、SNS等を活用した相談体制の整備推進等により、地方公共団体におけるいじめ問題等への対応を支援する。
地域におけるいじめ防止対策の体制構築を推進するため、こども家庭庁において、学校及び学校の設置者以外の首長部局からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証に取り組む。
Sport in Life推進プロジェクト(文部科学省/スポーツ庁)
一人でも多くの方がスポーツに親しみ、生活の中にスポーツが取り込まれている「Sport in Life」の実現に向けて、スポーツ振興に積極的に取り組む関係団体(民間企業、地方自治体、スポーツ団体、経済団体等)でコンソーシアムを構成し、加盟団体の自主的な連携による活動を促進させる仕掛けを施し、スポーツ実施者の増加に向けた推進力、相乗効果を創出する。